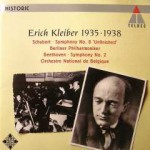2010年12月30日
ヘルマン・アーベントロート(1883年―1956年) 出身国:ドイツ

ブラームス:交響曲第1番
指揮:管弦楽:バイエルン国立管弦楽団
CD:DISQUES REFRAIN DR920035
ヘルマン・アーベントロートは、ケルン市の音楽監督をはじめ、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団常任指揮者(1934年-1945年)、ライプツィヒ放送交響楽団首席指揮者(1949年-1956年)、ベルリン放送交響楽団首席指揮者(1953年-1956年)を務めた経歴を見れば、大物指揮者であったことが分ろう。 過去に彼が務めた前任者や後任者の中に、ワルターやフルトヴェングラーなどの名前が見受けられることからしても、このことが裏付けられる。ただ、第2次世界大戦後は、東ドイツに留まったためか、わが国ではフルトヴェングラーやワルターほどには知名度は高くはない。しかし、彼の葬儀は東ドイツでは国葬が行われたというから、やはり凄い指揮であったのだ。
コメント/トラックバック投稿 »
2010年12月30日
エーリヒ・クライバー(1890年―1956年) 出身国:オーストリア
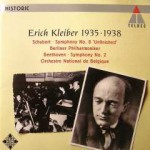
シューベルト:交響曲第8番「未完成」
ベートーベン:交響曲第2番
指揮:エーリッヒ・クライバー
管弦楽:ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(シューベルト)
ベルギー国立管弦楽団(ベートーベン)
CD:独TELDEC CLASSICS INTERNATIONAL 9031-76436-2
名指揮者エーリッヒ・クライバーのこのCDは、シューベルトの交響曲第8番「未完成」が1935年1月28日、ベートーベンの交響曲第2番が1938年1月31日と、今から70年以上前の録音にもかかわらず、いずれの音も豊穣で現在でも十分に鑑賞に耐えうるのには驚きだ。さすがに現在の録音のように、オーケストラの楽器の一つ一つ聴き分けられることはできないものの、オーケストラの全体の響きに訴える力があり、音にも安定感がある。オーケストラの場合は特に、楽器一つ一つの響きより、全体が醸し出す音の方が大切なので、このCDは今でも現役盤で十分に通用するといってもいいほどだ。そして、肝心の演奏の方も、指揮者のエーリッヒ・クライバーは、これら2曲の代表的名盤の一つといってもおかしくないほどの名指揮ぶりを、我々に披露してくれる。シューベルトの「未完成」は、誠に粋で曲全体が息づいているとでも言ったらよいだろうか。“小股の切れ上がったいい女”という表現があるが、クライバーの「未完成」は正にそんな感じがするのだ。決してべたべたしない、軽快であるがただ軽いのではない、優美さを兼ね備えた軽さなのだから、その魅力に触れるともう一度聴きかえしたくなる。
コメント/トラックバック投稿 »
2010年12月30日
ディミトリ・ミトロプーロス(1896年―1960年) 出身国:ギリシャ

ベートーベン:交響曲第6番“田園”
ボロディン:交響曲第2番
ディミトリ・ミトロプーロス指揮
管弦楽:ミネアポリス交響楽団(ベートーベン)/ニューヨークフィル(ボロディン)
CD:伊IRONNEEDLE
ディミトリ・ミトロプーロスはアメリカで活躍した名指揮者だ。このCDは1940年に録音されたもので、音質の状態は万全ではないが、ミトロプーロスの偉大さの片鱗を窺い知ることができる。その指揮ぶりは躍動感あふれるもので、CDを聴いてるだけでも生き生きとした指揮ぶりに惚れ惚れする。フリッチャイに似たリズム感ではあるが、一方では、あたかもワルターのように雄大な巨匠風の指揮ぶりも見せ付けて、聴いていて飽きが来ない。ベートーベンの“田園”をこんなに劇的に指揮した録音は聴いたことがない。全曲これミトロプーロス節といった趣であるが、ぜんぜん嫌味がないところがさすがと感じさせる。
コメント/トラックバック投稿 »
2010年12月30日
エフゲニー・ムラヴィンスキー(1903年―1988年) 出身国:ロシア出身

~新ムラヴィンスキーの芸術~<ライブ録音盤>
モーツアルト:交響曲第39番
グラゾノフ:組曲「ライモンダ」
ワーグナー:歌劇「ローエングリン」から第3幕への前奏曲
指揮:エフゲニー・ムラヴィンスキー
管弦楽:レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団
演奏はというと、どれを取っても曲の本質を、一切の贅肉をそぎ落とし、しかも少しも、ぎすぎすしたところがなく、しかもある意味では豊穣な香りが立ち上る感覚を覚えるところが、ムラヴィンスキーの指揮の凄いところだ。例えば、ムラヴィンスキー同様、トスカニーニも余計な贅肉をそぎ落とした指揮をするのだが、トスカニーニは筋肉質の緊張感が表面に出てくる。それに対し、ムラヴィンスキーは、豊かな詩情を残しながら、しかも演奏の本質は筋肉質で無駄はない。言ってみればトスカニーニとワルターとを足して二で割ったような印象を持つ。足してニで割ると言っても、決して2者の中間という意味でなく、あくまで独自の主張を持った曲づくりがその中心にある巨匠であることが、このCDを聴くとよく分る。
コメント/トラックバック投稿 »