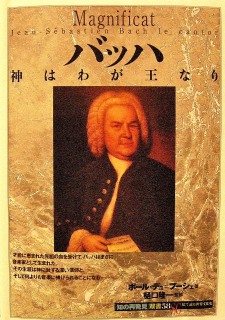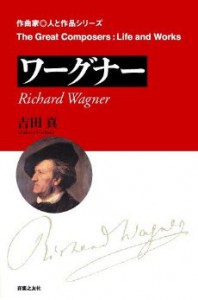2014年12月02日

書名:モーツァルト
著者:礒山 雅
発行:筑摩書房(ちくま学芸文庫)
目次:第1章 生涯
第2章 「貧しいモーツァルト」というフィクション
第3章 最後の年一七九一年(1)―開かれた扉
第4章 最後の年一七九一年(2)―終息に向けて
第5章 伝記はどう作られたか
第6章 自分でつけた作品目録
第7章 歌曲に秘められたドラマ
第8章 オペラにおける人間描写―フィオルディリージの場合
第9章 発展する交響曲
第10章 モーツァルトとバッハ
モーツァルトを知るための15曲
モーツァルトに関する書籍は、クラシック音楽の書籍の中で最も多いのではなかろうか。それだけ、クラシック音楽ファンにとっては、モーツァルトの存在は大きなものと言えよう。逆に、モーツァルトの書籍が多いので、その中のどの書を読めばいいのか、選択に戸惑ってしまう。それらは、モーツァルトの年代に沿って活動を紹介していく形式の書が一番多いのではなかろうか。さらに、作品の分析に重点を置く書、CDに収められた演奏比較の書なども多いと思う。ちくま学芸文庫の一冊として発刊された「モーツァルト」(礒山 雅著、筑摩書房)は、著者の「モーツァルト=二つの顔」(講談社選書メチエ)の文庫本化に際し、新たにモーツァルトの生涯を辿った章を付け加えて発刊された。このことによって、携帯しやすい文庫本化が実現したうえに、モーツァルトの生涯から始まって、作品の分析・比較、作品目録、そして厳選15曲のとそれらの推奨CD・DVDの紹介に至るまで、モーツァルトの全てが収められた書籍が完成することになった。これはモーツァルトを1冊で知りたいという人にとっては最良の書となろう。
「第2章『貧しいモーツァルト』というフィクション」では、学生の間に「貧しいモーツァルト」というイメージが定着していることに筆者が驚くことから始まる。そしてモーツァルトの「モーツァルトのふところ具合」の詳細な検討へと進んで行く。メイナード・ソロモンが推定した結果によると、モーツァルトの年収は、1784年をピークに減少の傾向を示し、1788年から1790年に掛けて低迷した後、最後の年に著しく上昇しているという。つまり、作品を多産した年の収入が減ることの謎解きから分析が進んでいく。モーツァルトの生活は、全体に優雅なもので決して貧困にあえいでいたわけではないようなのである。どうも浪費癖があったようで、このことが一般に「貧しいモーツァルト」イメージとなったらしい。要するに常に借金しては返し、また借金を繰り返す生活をしていたらしい。そこには金銭感覚に疎い芸術家の姿が浮かび上がる。さらに驚いたことにモーツァルトは、当時流行った「ファラオ遊び」というトランプの賭けに熱中していたようだ。これにより“モーツァルト・ギャンブラー”説も持ち上がる。
「第3章 最後の年一七九一年(1)―開かれた扉」と「第4章 最後の年一七九一年(2)―終息に向けて」の2つの章は、モーツァルトが死を迎える1年の間にに書かれた作品の分析に当てられている。筆者は言う。「モーツァルトは、成功したいという望みを長年にわたって抱き続けた人である」と。その証拠に「彼の手紙には、成功への願望が、どれほど頻繁にあらわれることだろうか」とモーツァルトの成功願望の強さを強調する。ところがモーツァルトは最後の年を迎える頃になると「そんな成功へのこだわりを捨てたように見える。捨てたというのが言い過ぎであれば、彼は成功をもっと広い視野で捉えるなったと思われる」ようになって行く。「成功を人に向けて考えるのではなく、純粋に音楽に向けて、あるいは音楽の神様に向けて考えるようになったと、私は言いたい」と結論付ける。筆者は、このことが結実した作品の一つが、モーツァルトから肩の力が抜け、穏やかで幸福感に満ちた変ロ長調のピアノ協奏曲第27番であると指摘する。なるほど、ピアノ協奏曲第27番を思い起こすと、何かこの世のものとも思われない、天上の音楽でも聴くような雰囲気がする。
「第6章 自分でつけた作品目録」では、モーツァルトがその後期に、自分の作品目録である、通称「自作品目録」をつくった経緯が詳細に紹介される。また、モーツァルトの父レオポルドも「この12歳の子供が7歳時以来作曲した全作品の目録」を作成している。そして、1862年にケッヒェルにより、「ヴォルフガング・アマデ・モーツァルトの全作品の年代順主題目録」が刊行される。さらに、研究が進むにつれて改訂版が発刊され、アインシュタインにより、617a=356というような二重番号制を採用した改訂版が発刊される。そして現在においては、1964年のケッヒェル第6版に辿り着く。話はこれで終わりではなく、さらにザスラウにより「新ケッヒェル」の編纂が行われているという。作品目録一つとってもモーツァルトの研究は、大きなドラマがその背後に控えているのだ。さらに同書では、モーツァルトの書いた歌曲、オペラ、交響曲、そしてモーツァルトとバッハの詳細な分析が行われ、読者は「なるほど、そういうことだったのか」と納得させられ、思はず同書に釘付けになることであろう。そして最後に「モーツァルトを知るための15曲」が掲載されている。ここでは、知る人ぞ知る的なCD、DVDも紹介され興味深い。また、同書には、詳細な人名索引と楽曲索引が付けられているので辞書的な活用も可能だ。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2014年7月22日

書名:作曲家ダイジェスト ラフマニノフ (CD付)
著者:芝辻純子・堀内みさ
発行:学研パブリッシング
目次:<作曲家を知る>
1.幼少期のラフマニノフ
2.ラフマニノフが学んだ先生と学校
3.音楽家ラフマニノフ
4.ラフマニノフの交友録
5.はじめての挫折
6.ロシア音楽の系譜
7.ラフマニノフの性格と結婚
8.当時のロシアと欧州情勢
9.“指揮者”ラフマニノフと演奏活動
10.隠れた名曲
11.アメリカへの移住と望郷
番外編1.ラフマニノフ作品と映画
番外編2.名曲名盤案内
番外編3.ラフマニノフゆかりの地
<名曲案内>
1.ピアノ協奏曲第2番
2.パガニーニの主題による狂詩曲
3.12の歌
4.幻想的小品集
5.ピアノ協奏曲第1番
6.歌劇「アレコ」
7.組曲第1番「幻想的絵画」
8.楽興の時
9.14の歌曲
10.ピアノ三重奏曲第2番「偉大な芸術家の思い出」
11.組曲第2番
12.チェロ・ソナタ
13.ショパンの主題による変奏曲
14.10の前奏曲/13の前奏曲
15.12の歌
16.交響曲第2番
17.交響詩「死の鳥」
18.ピアノ協奏曲第3番
19.合唱交響曲「鐘」
20.ピアノ・ソナタ第2番
21.無伴奏合唱曲「晩とう」
22.練習曲集「音の絵」
23.コレルリの主題による変奏曲
24.ピアノ協奏曲第4番
25.交響曲第3番
26.交響的舞曲
ラフマニノフゆかりの街MAP
ラフマニノフ関連年表
付録CD収録曲一覧
「作曲家ダイジェスト ラフマニノフ(CD付)」(芝辻純子・堀内みさ著)は、ラフマニノフの生涯とその作品を、まずは一通り知りたい人達にとっては、格好の書と言える。それは、簡潔な文章(1テーマについて見開き2ページ)で綴られているうえ、豊富な写真が掲載されているので、ラフマニノフという作曲者の実像がつかみやすい点にある。<作曲家を知る>と<名曲案内>の各項目が交互に掲載されており、初心者が読み易く単調に陥らないような配慮もされている。ただ、後で資料的に使う時には、それぞれ別個に掲載された方が便利かもしれない。読みやすい工夫はほかにもある。「ラフマニノフ作品と映画」「名曲名盤案内」「ラフマニノフゆかりの地」からなる3つの番外編は、ラフマニノフの姿を印象付けるための手助けとなろう。このほか「ラフマニノフゆかりの街MAP」「ラフマニノフ関連年表」も掲載されている。さらに、代表作27曲の一部が収められているCDが付いているので、知らない曲があれば直ぐにでも聴くことができるので便利だ。
ラフマニノフの音楽は、昔懐かしい何かを感じさせてくれる。全ての作品に歌のメロディーが流れているようでもあり、メランコリックな感触も素晴らしい。その昔、私は、ドイツ・オーストリア系の作曲家の作品をもっぱら愛好していた。それ以外はというとせいぜいショパンまでで、ラフマニノフの作品は、ほとんどと言っていいほど聴かなかった。ただ、「ヴォカリーズ」と「パガニーニの主題による狂詩曲」第18変奏曲については、何と美しい曲なのだろうという印象があり、愛聴していたが、当時、それ以上にラフマニノフの音楽を系統だって聴くことはなかった。
ところが、ある時何気なく、ラフマニノフの交響曲第2番を聴いたとき、正直、こんなに心を打つ交響曲は滅多にあるものではないと驚いたことがあった。この交響曲第2番は、昔は、縮小版によって演奏されるのが通常であったそうだが、初めてアンドレ・プレヴィンが全曲版を指揮し、その全容が広く世界に知られるようになったわけだが、そのプレヴィンがロンドン交響楽団を指揮したラフマニノフの交響曲第2番のCDのライナーノートでプレヴィンは、次のように述べている。「・・・私の音楽生活において最も忘れがたい出来事の一つは、この交響曲の演奏中、モスクワの聴衆が公然と人目をはばかることなく、泣いているのを知ったときでした。・・・」アンドレ・プレヴィンというとアメリカ人のような印象を持つが、実は親はロシア人であり、ロシアの血が流れているラフマニノフに対する思いは、人並み以上なのだろう。
ラフマニノフを理解するにはロシアの風土の理解無くしてはあり得ないかもしれない。ロシア系のピアニストがドイツ・オーストリア系の作曲者の作品を弾かないケースはほとんどないであろうが、逆にドイツ・オーストリア系のピアニストがラフマニノフの作品の演奏しないケースがある。このことは、ロシア音楽独特の雰囲気に素直に入っていけるかどうかが鍵を握っているようだ。ラフマニノフというと、先輩のチャイコフスキーを思い浮かべるが、チャイコフスキーは、意外に西洋風な作風も多く取り入れており、ヨーロッパの演奏家からすると、チャイコフスキーの方が、ラフマニノフよりは取っ付きやすいということが言えそうである。しかし、ラフマニノフの世界に一旦入ってしまうと、その魅力からそうやすやすと抜け出せなくなるのも確かだ。この「作曲家ダイジェスト ラフマニノフ(CD付)」(芝辻純子・堀内みさ著)は、よりラフマニノフという作曲家を理解したい人に加え、今一歩ラフマニノフの世界に入り込めてない人にも大いに参考になる書だ。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2014年6月10日

書名:バロック音楽
著者:皆川達夫
発行:講談社(講談社学術文庫)
目次:はじめに
バロック音楽との出会い 音楽とはなにか
1.ヨーロッパ音楽の流れ
2.バロック音楽の魅力
3.楽器が語るバロック音楽
4.オペラと宗教音楽 イタリアの声楽音楽
5.新しい様式を求めて イタリアの器楽音楽
6.優雅な宮廷音楽 フランス
7.革命と音楽の運命 イギリス・スペイン
8.「音楽の国」の誕生 ドイツ
9.バロック音楽の大成 バッハとヘンデル
バロック音楽と日本人ー結びーわれわれを取り巻く音楽的状況
あとがき
バロック音楽史小辞典
バロック音楽史年表
バロック音楽史関連地図
事項索引
人名索引
「バロック音楽」(皆川達夫著/講談社学術文庫)は、1972年11月に講談社現代新書として刊行されたものを原本として、2006年3月に講談社学術文庫として新たに発刊された。文庫版として発刊されたことでコンパクトとなり、持ち歩くのには大変便利であるうえ、その内容は、これ1冊でバロック音楽のことなら何でも載っており、読み終えた際には、バロック音楽の世界が俯瞰できるように構成されている。付録(?)の「バロック音楽史小辞典」「バロック音楽史年表」「バロック音楽史関連地図」「事項索引」「人名索引」のいずれもが簡潔に、しかも重要な点は漏らさず網羅されているので、これだけでも一つのバロック音楽辞書として発刊できるのでは、と感じられるほど。バロック音楽の書籍はいうに及ばず、CDやFM放送により、現在、バロック音楽を自由に聴くことができる時代が到来しており、我々は恵まれた環境にあると言ってもいいであろう。しかし、バロック音楽のことを、どのくらい正確に把握しているかというと、どうも怪しいことになってくる。しかし、勉強しようにも内容があまりに専門的で難解な書籍では、なかなか読みこなせない。そんな人には、この書は打って付けだ。バロック音楽が分かりやすく、懇切丁寧に解説されているからである。
一般のバロック音楽解説書が、いきなりバロック音楽から始まるのに対し、この書は、「1.ヨーロッパ音楽の流れ」として「バロック以前の音楽」「バロック音楽以後の音楽」から始まるので、まずは西洋音楽の大まかな流れを掴み、バロック音楽の話に入る前の準備運動ができるので大いに助かる。この辺の配慮は、著者が単にバロック音楽の知識を解説するだけではなく、バロック音楽の愛好者を増やしたいという熱意のようなものがその背後に感じ取れる。著者は、「バロック音楽との出会い」の中で「現在の幅広いバロック音楽の愛好者の存在を説明しうる最大の理由は、バロック音楽が一切の先入観や観念を必要とせず、虚心に音の美しさにひたりきらせる純粋さと楽しさとを蔵していることであろう。それは純粋であるだけに、聞く者の心に応じた多様性の接近が可能である。ジャズを愛好する人々の中にも、少なからずバロック・ファンが存在し、バロック音楽のジャズ化さえ行われているありさまである。現代の生活に疲れた心は、バロック音楽の純粋な音の流動な中に、憩いと癒しを見出しているいえようか」と書いているが、「私もそう思う」と思わず共感したくなる。この書は、「何故今、バロック音楽なのか」についての回答の書であるのかもしれない。
西洋音楽を勉強する時に、バロック音楽は欠かせない要件だ。バロック音楽と聞くと、何か古めかしい音楽ということだけが頭にこびり付いていると、バロック音楽のホントの姿を見失いがちになる。著者は、「バロック芸術は劇の原理が支配する芸術であり、運動と変化とを追求する芸術である。音楽においてもまた同様であった。大バッハの『マタイ受難曲』は、おそらく人類が作りえた最大の劇音楽ー音楽で表現された最高の劇ではないであろうか。聞く者を最後まで引き付け、引きまわしてゆくあの不思議な説得力は、バッハならではのものであり、またバロック芸術ならのものである。・・・ある見方をすれば、音楽とは本来バロック的な芸術であり、その意味ではバロックとは一定の年代や時代に関わりなく、また洋の東西を問わず、つねに音楽のあり方、芸術のあり方、そして文明のあり方に関わりあうものといえなくもない」と指摘する。つまり、バロック音楽は、ただ古いものなどでなく、時代を越え、国境を越えた普遍性を持った芸術なのだという。バロックとは、“ゆがんだ真珠”の意味を持つが、当時の人にとっても、そのダイナミックな動きは、驚きを持って迎えられようだ。そして、今、アジアの一島国の我々日本人にも多くの愛好者を持つバロック音楽は、21世紀の音楽として、今後も力強く生き続けようとしている。
同書では、国別のバロック音楽の発展の動きを詳細に解説している。我々日本人は、よく西洋文化を考える場合、ヨーロッパ全域に共通する何かを見出そうとする。しかし、アジアを見ても分かる通り、西洋文化を一様に眺めようとしても、個々の国の状況を把握しなければ、全体像は到底分からない。その点、同書では、「オペラと宗教音楽 イタリアの声楽音楽」「新しい様式を求めて イタリアの器楽音楽」「優雅な宮廷音楽 フランス」「革命と音楽の運命 イギリス・スペイン」「『音楽の国』の誕生 ドイツ」「バロック音楽の大成 バッハとヘンデル」のタイトル通り、それぞれの国で活躍した作曲家一人一人の足跡を辿りながら、その国におけるバロック音楽の特徴を浮き彫りにする。ここまで読み進めると、自然にバロック音楽の基礎知識を身に着けることができそうだ。さらにその後には「バロック音楽と日本人~結び~われわれを取り巻く音楽的状況」というタイトルが飛び込んでくる。筆者は、ヨーロッパ各国ごとのバロック音楽の解説で終わらず、日本とバロック音楽との結び付きにも言及する。西洋音楽が日本に入って来状況の解説に加え、筆者は、現在の日本の音楽状況に厳しい指摘をする。「今日なお、日本においては、クラシック音楽は文化の片隅の好事家の業である。音楽を除いて一国の文化は存在しえないという、欧米ではしごく当然の認識が日本では、まだ確立されていない」と今日の日本の状況に警鐘を鳴らしている。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2014年4月08日

書名:グスタフ・マーラー~現代音楽への道~
著者:柴田南雄
発行:岩波書店(岩波現代文庫)
目次:第1部 グスタフ・マーラー~現代音楽への道~(出典:岩波書店、1984年10月)
はじめに―われわれとマーラー
1 ボヘミアからヴィーンへ
2 新しい世界への出発
3 成就と崩壊の始まり
4 背後の世界の作品
5 開かれた終末
あとがき
第2部 マーラー小論
交響曲第1番ニ長調「巨人」(出典:青土社、1986年9月)
交響曲第5番嬰ハ短調 (同)
マーラー・ブームが意味するもの―クラシックの現在(出典:岩波書店、1990年10月)
「グスタフ・マーラー~現代音楽への道~」は、大きく分けて、第1部グスタフ・マーラー、それに第2部マーラー小論の2つから構成されている。第1部は,岩波新書「グスタフ・マーラー現代音楽への道」として岩波書店より1984年10月に刊行されたもので、2010年に新たに、第2部マーラー小論と合わせて、岩波現代文庫として発刊された。内容は、交響曲 第1番~第10番、それに「大地の歌」についての著者の解説が中心となって構成されている。つまり、マーラーが作曲した作品を順番に辿ることによって、マーラー像を浮かび上がらせるという内容だ。さらに、当時の日本のマーラーの交響曲の演奏会の情景も織り込まれていることで、日本におけるマーラーの交響曲演奏史を知る上では、貴重な証言にもなっている。マーラーと言うと、直ぐにブルックナーとかワーグナーを思い描くが、これらの中にあって最近においては、マーラーの評価は高まっているのではないかと思う。それは、現代人が漠然と感じている不安とか恐れ、さらにそこから逃れようと葛藤する様が、マーラーの作品そのものに内蔵されているためだからであろう。ブルックナーは、宗教的色彩が濃く、またワーグナーは、最近現代的解釈がなされているとしても、基本はギリシャ悲劇が題材だ。それに対してマーラーの作品は、宗教色は薄いし、無調音楽など当時新たに勃興した現代音楽的要素も作品にいち早く取り入れ、新しいクラシック音楽としての感覚が共感を呼ぶのであろう。
著者の柴田南雄(1916年ー1996年)は、作曲家と同時に音楽評論家、音楽学者として多くの著書を残している。また、ラジオなどで音楽解説を幅広く手掛けていた。音楽は独自に学んでいたようではあるが、1936年に東京帝国大学理学部植物学科に入学し、さらに大学院で植物学を研究、東京科学博物館植物学部に勤務したというから、人生のスタートは植物学者だったのだ。その後一転し、東京帝国大学文学部美学美術史学科に入学。卒業後、音楽協会などの職員を経て、子供のための音楽教室(桐朋学園大学音楽科の前身)の設立に参加している。その後、本格的に音楽家の道に進み、東京藝術大学の教授も務めた。そんな経歴を持つ著者だけに、「グスタフ・マーラー~現代音楽への道~」は、内容も単なる楽曲解説の範疇を越え、文明評論的意味合いを含んだものに仕上がっている。「近年のマーラー復興は結局のところ、今日の世相とマーラーの時代の世相との間になんらかの共通点が存在するからではないのか。・・・世紀末的な、あるいは戦争前夜の危機感、その予感といったものを人々は無意識にせよ、マーラーの音楽から感じ取っているのではあるまいか」。これは、今から30年前の柴田南雄の文章であるが、今でもそのまま通用しそうだ。
今から30年も前の著作であるから、当時の日本における演奏会風景の紹介にも興味が引かれる。「わたくしのマーラーの『第8交響曲』の体験は、まず本邦初演の、1949年12月の日本交響楽団(今のN響)の定期演奏会であった。指揮の山田一雄の獅子奮迅の勢いというか、阿修羅のごとき活躍というか、あの熱演、激演は普通のものではなかった。・・・もう一つ忘れられない『第8交響曲』の演奏と言えば、早稲田大学創立100周年記念を機に開かれた、同大学のオーケストラ、同大学学生の合唱団に東京の諸大学の合唱団が加わっての公演(1982年10月24日)である。指揮者の岩城宏之のほかはオール・アマチュアであった」。当時のわが国のクラシック音楽の状況は、今より、若者が多く参加していたように思う。特に、マーラーには、どことなく現代音楽的な香りがして、自分たちが、これからの新しいクラシック音楽界をつくろうという熱き思いが充満していたのではなかろうか。現在、現代音楽は、一般大衆からは離れた存在となってしまっている。現代音楽の理解者でもあった柴田南雄が、今もし健在であったなら、現在の日本のクラシック音楽界をどのように評論するのであろうか。
同書の第2部マーラー小論は、3つの小文が掲載されている。これらは第1部の要約版的な意味合いをもつもので、手軽に柴田南雄のマーラー観を知りたいのであれば、この第2部から先に読むのも一方法であろう。「問い:マーラーという人の作風は、当時として、進歩的だったんでしょうか。柴田:進歩的ですね。しかも一作ごとに絶えず新しい構成を考えています。ただ、調性的な線に固執したこと、リズムや拍子が定型的なことなど、保守的な面もありますけれども」 「問い:シューベルトとマーラーは、作風の上でかなり似ていると思いますが。柴田:それはもう、いわゆるヴィーン風の感じがじつに共通してますよ。レートリヒという学者が、交響曲第1番の第3楽章のテーマがシューベルトの第9番の第4楽章、第2主題と関係があると言っているらしいのですが、あちこちに似た点はたしかに出て来ますね。まあ、やはり歌謡風のモチーフをよく用いる点が第一でしょうね。それからいわゆるレンドラー舞曲、オーストリアの田舎の踊りですね。その感じは区別がつかないくらいそっくりですね」「問い:第1番から第4番まで一つの一貫した発展の方向というのは、技法的な問題についておっしゃっているのでしょうか?柴田:一言で言えば、主題の解体と副次的なモチーフの数をだんだん増やしていくという傾向ですが、それが第5番では一変して、ある旋律パターンの有機的なメタモルフォーゼという方法がとられるようになり、これがそれ以後のシンフォニーの中に受け継がれていく。この変化は、言ってみれば第4番までのベートーヴェン=ワーグナー的世界から、第5番でシェーンベルク的な世界への転換だと思うのです」。柴田南雄は、クラシック音楽は世界音楽へと発展的に解消されることを予言していた。そして、その転換点に当たるのがマーラーなのだ、と言う。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2014年1月28日

書名:ベートーヴェンとベートホーフェン~神話の終り~
著者:石井 宏
発行:七つ森書館
目次:プロローグ
第1章 盛名
第2章 有名人の肖像
第3章 ゲーテとベートホーフェン
第4章 女たちの影
第5章 〝不滅の恋人〟
第6章 愚行
第7章 革命的な音楽家
第8章 栄冠
第9章 終章
巻末付録=〝不滅の恋人〟への手紙
ベートーヴェンは“楽聖”とも呼ばれ、クラシック音楽の作曲家の象徴的存在であることは、紛れのない事実であろう。特に日本人は、ベートーヴェンを神のごとく慕う傾向が特に強いのではないだろうか。“第九”と聞けば、クラシック音楽ファンならずとも、ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱」のことだと誰もが分かる。つまり、ベートーヴェンは完全に神格化されており、少しもこれを疑う余地はない、と皆が考え、逆に“楽聖”であるベートーヴェンを少しでも疑おうものなら、方々から石が飛んできそうな雰囲気さえある。しかし、あまりの神格化は、実像を歪んだものにしがちであり、ベートーヴェンとてその例外でない。石井 宏著 「ベートーヴェンとベートホーフェン~神話の終り~」は、神格化されたベートーヴェン像を一つ一つのテーマについて、あたかも事件を追う刑事のごとく、地道な調査と大胆な推理とを巧みに組み合わせて厚いベールを剥ぎ取り、ベートーヴェンの実像に迫る、という力作なのである。構想に3年、執筆に2年をかけた、書き下ろしであるというから、筆者の覚悟のほどが分かるというものだ。筆者の石井 宏氏は、1930年生まれで、東京大学文学部美学科・仏文科を卒業。モーツァルトの評論の第一人者として多くの著作がある。また、2004年には、「反音楽史 さらば、ベートーヴェン」(新潮社)で山本七平賞を受賞している。
もともと、クラシック音楽の作曲家は、モーツァルトの時代までは、社会的な地位は高くなく、そのこともあり、モーツァルトの墓はない。今、聖マルクス墓地にあるモーツァルトの墓にモーツァルトが眠っているわけではない。共同墓地に集められ、埋められた遺骸に紛れ込んでしまったので、モーツァルトの墓は見つからないのだ。それに対し、ベートーヴェンの葬儀には2万人の群衆が押し寄せたというから、その差はあもりにも大きい。この差は何を意味するのか。ベートーヴェンの偉大な業績もあったろうが、ベートーヴェンの時代になり、作曲家もようやくスターの仲間入りをしたということも大きく影響したのだ。筆者は、この辺から解き起こし、あたかも推理小説のごとくベートーヴェンの実像に徐々に迫って行く。ところで、この書の題名「ベートーヴェンとベートホーフェン」とは何か?ドイツ語読みでは、我がベートーヴェンは、ベートホーフェンと発音される。では、ベートーヴェンは? 何でもベートーヴェンの先祖はオランダ系で、昔のドイツ人がオランダ読みでルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェンと発音したのが始まりだとか。ちなみに、ヴァン・ベートーヴェンをオランダ語で解釈すると“赤カブ畑の出身”を意味するそうで、このことからベートーヴェンの先祖は、農夫と推察されるという。この辺は筆者の真実を何とか探り出そうとする情熱がひしひしと伝わってくる。後々このベートーヴェンのこの“ヴァン”が貴族出身を連想させることから、あらぬ騒動を引き起こしていくことになるのだが。
ベートーヴェンの神格化の決定的な証拠が、残された肖像画である。筆者は「第2章 有名人の肖像」において、残された何種類もの肖像画を1枚、1枚克明に検証していく。我々が接するベートーヴェンの肖像画は、ペンを持ち、苦悩の面持ちで一点を見つめている、1820年にシュティーラーが描いたあの有名な肖像画である。この肖像画なら“苦悩を通して歓喜に至る”ベートーヴェンにピタリと合う、ということで、ベートーヴェンというとあの有名な肖像画を多くの人がまず最初に思い浮かべる。しかし、実際のベートーヴェンの姿は、それとは全く違っていたようなのだ。「彼は背が低く(シンドラーによると155センチくらい)、色が黒く、髪も真黒だというからには、金髪で背の高いふつうのドイツ人の中では、異色の存在であったろう。そのうえ、蓬髪でアバタだらけとなると、どう見ても女にもてる顔ではない」「晩年のベートーホーフェンはむさくるしい恰好をして深夜の街をうろつくので、あるとき、浮浪者と間違えられて、留置所に入れられてしまった。捕まった男は昂然たる態度で『おれはベートホーフェンだ。今すぐここから釈放するようにメッテルニヒに言いたまえ』と言ったという」これらの文章を読むと、従来我々が持つイメージとは大分かけ離れている。しかし、よく考えてみると、晩年作曲に没頭していた時のベートーヴェンの実像は、これにかなり近いことは容易に想像できる。もう、周囲のことにはお構いなしに作曲に没頭すれば、髪もぼさぼさであろうし、髭も剃らなかったであろう。そんな姿で夜の街を歩いていたら、浮浪者と間違えられてもしょうがないのかもしれない。筆者が言いたかったのは、美化されベートーヴェン像でなく、真実のベートーヴェン像なのである。
このように、同書はベートーヴェンの実像に迫るため、あらゆる角度から次々と検証していく。「〝不滅の恋人〟とはいったい誰なのか」「甥カールとの関係は」「ゲーテとの関係」などなど、あらゆる検証が最後まで続く。読み終えると、どうして従来のベートーヴェン像と真実のベートーヴェンとがこうも食い違うのか、という謎が自然と湧き起こってくる。その答えは、ベートーヴェンの生きていた時代背景に求めることができる。「時代はまさに、プロイセンを代表とするドイツが、国内統一とヨーロッパの覇権を目指す時期にあった。政治的にも、文化的にも、彼らは先進のフランス、イタリア、スペインなどのラテン系諸国やアングロ・サクソンに対して、“追い付き追い越せ”の旗印を掲げて走り出したところであった」これで少し分かってきたぞ。どうも天才作曲家であるベートーヴェンの存在と政治が関係しているようである。悪く言えば、政治がベートーヴェンを利用したのではないのか。「ドイツ人の学者たちは、まもなくこのベートホーフェンの音楽を頂点とした音楽史観を作り上げ、音楽とは崇高なものでなければならず、それはとりもなおさず、ドイツ人の器楽のことであり、その器楽の規範はベートホーフェンとソナタ形式にある、としたものである。・・・この史観は独り歩きを始め、何も知らない日本人やアメリカ人を巻き込んで、居座った」ああなんということか。従来のベートーヴェン像は、意図的につくられた虚像のようなものだ、というのだ。そして、筆者が探し求めていたものは、“等身大のベートーヴェン像”だということが最後になって分かってくる。“等身大のベートーヴェン像”を明らかにすることは、少しも“楽聖”ベートーヴェンを損ねないし、逆に人間臭いベートーヴェンが苦闘して“楽聖”にまでに昇り詰めることができたということが理解できる。“等身大のベートーヴェン像”を知ることは、多くの人に、ベートーヴェンの偉大な業績により深い尊敬の念をもたらすことに繋がるのではなかろうか。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2013年11月04日

書名:世界でいちばん貧しくて美しいオーケストラ ―エル・システマの奇跡―
著者:トリシア・タンストール
訳者:原賀真紀子
発行:東洋経済新報社
目次:プロローグ:ドゥダメルの衝撃
第1章:バーンスタインの再来
第2章:エル・システマの躍進
第3章:革命家アブレウ
第4章:踊るオーケストラ
第5章:音楽が大陸をつなぐ
第6章:才能を開花させる子どもたち
第7章:広がる教育プログラム
第8章:市民音楽家ドゥダメル
クラシック音楽は、西洋の宗教音楽に始まり、貴族の音楽を経て、市民の音楽へと発展を遂げ、そして現代音楽へと行き着いた。これからクラシック音楽は何処に向かおうとしているのであろうか。残念ながら、その答えは、まだ見えてきていないようである。それどころか、「これまでクラシック音楽は、あらゆる可能性を試み、発展してきたが、これ以上の広がりは期待しにくい」と指摘する向きもいることも事実だ。今から少し前の時代、いわゆる現代音楽が脚光を浴びた時期は、「これから新しいクラシック音楽が切り開かれて行くに違いない」と多くの人が考えていた。当時、「これからはバッハやベートーヴェンは過去の時代の音楽となり、現代音楽がそれに取って代わる」と断言していた人もいたぐらいだ。ところが、その現代音楽は期待に反して、大きな広がりを見せることはなく、足踏み状態にあると言っても過言ではないであろう。つまり、クラシック音楽は、袋小路に入り込んでしまったというのが現実の姿だと私は思う。逆に、過去のクラシック音楽への再評価がなされ、その結果、古楽器演奏のブームなどが起きたりしている。これはこれで、何も問題はないのであるが、何か釈然としないことも確かだ。
日本の歌舞伎は、国からの援助なくして公演を行っている一方、聞くところによるとヨーロッパの歌劇場は国からの援助なくしては成り立っていないのが現状であるらしい。これは、日本において、ヨーロッパのオペラ公演が目白押しに行われていることを見れば、何となく理解できる。日本人は、歌舞伎は古くて、オペラは新しいと思っているかもしれないが、必ずしもそうとも言えない。芸術においてもその経済的基盤が、その時代の評価に繋がるものだ。そんな中、日本のクラシック音楽界も手をこまねいているわけではない。オーケストラが子供向けのコンサートを企画したり、演奏家が安い料金で演奏会を開催したりと、いろいろと努力はしている。しかし、現状ではどうも根本的な解決策には至っていないようにも思われる。これはクラシック音楽界の体質と密接な関係がある。多くの場合、クラシック音楽で身を立てようとすると、音楽大学に入り、卒業後は欧米に留学し、有名コンクールで1位にでもならなければ、将来は明るくない。つまり、現在のクラシック音楽の道を進もうとすると、経済的にかなり恵まれた人しか道は開かれていないのである。だから、今、クラシック音楽のコンクールで1位を獲っても、それは金銭的に恵まれた人の中での1位であって、必ずしも全才能の中の1位を意味するものではない、というのが私の持論である。
そんな中、現在、世界のクラシック音楽界で注目を浴びているのが、ベネズエラにおいてホセ・アントニオ・アブレウ氏が1975年に始めた音楽教育活動「エル・システマ」である。そして、この「エル・システマ」の全貌をくまなく紹介しているのが今回の書籍「世界でいちばん貧しくて美しいオーケストラ―エル・システマの奇跡―(トリシア・タンストール著/原賀真紀子訳/東洋経済新報社)」なのである。ベネズエラは、正式な国名をベネズエラ・ボリバル共和国と言い、南アメリカ北部に位置する連邦共和制社会主義国家で、首都はカラカス、人口は2858万人。まず、驚かされるのが、クラシック音楽が何故ベネズエラなのか、という点。これまでクラシック音楽というと本場のヨーロッパあるいは北米、それに最近ではアジアが台頭してきているが、南米のベネズエラとの関係が結び付かない。実は、ここにクラシック音楽の盲点があったのだ。これまで経済的な豊かさとクラシック音楽は結び付いてきたが、貧困層とは縁のない音楽だと見なされてきた。それを180度がらりと変え、アブレウは「貧困層だからこそクラシック音楽教育が必要だ」と主張し、始めたのが音楽教育活動「エル・システマ」なのである。これは世界中誰も考えもしなかった発想である。しかし、そんなことホントにできるのか、という疑問が出てくると思うが、今では40万人の子供が300以上の教室に通っているというから成功しているのだ。しかも、世界に通用する才能が育ちつつある。それは、今世界中で絶賛を浴びている10代~20代の青少年からなるシモン・ボリバル交響楽団であり、次期ベルリン・フィルの音楽監督就任の呼び声も高い、若き指揮者のグスターボ・ドゥダメルなのである。
貧困層と言ってもどれほどのものなのか。少々長くなるが同書から拾ってみよう。「痩せっぽちで用心深い目をした9歳のエステバン君は、カラカス市内の貧困地区で暮らしている。ここは掘立小屋のような家が丘の斜面にひしめき合っている。水が出ないこともあれば、電気のつかないこともある。どちらもダメ、という日もある。夜、怒鳴り声やエンジンをふかす音が聞こえてくると、妹は怖がって眠れない。兄は15歳で学校に行かなくなり、家にも寄り付かなくなった。ギャングに入ったのだ。父親は刑務所で服役中。最後に会ったのはいつだったか覚えていない」。今の日本からすると想像を絶する貧困さだ。日本であったなら、こんな貧困家庭では音楽なんかとんでもないということになろう。「エステバン君は、学校で先生から『お前はばかだ』と言われた。でも、1年前からシステマでヴァイオリンを習い始めて、自分は愚かでないことを知った。今ではモーツァルトやヴィヴァルディの曲を弦楽アンサンブルで弾いている」。最初に、クラシック音楽界が今袋小路に入っている、と書いたが、袋小路を出るヒントをこの「エル・システマ」は教えてくれている。つまり、クラシック音楽を、偏見を持たずに、もっと多くの人に参加してもらうことだ。「エル・システマ」は既に世界中に広がりを見せ、日本でも「エル・システマジャパン」が設立され活動を行っている。「エル・システマ」の活動で大切なのは、クラシック音楽を“楽しむ”ということ。「エル・システマ」では、演奏しながら踊り出すこともあるという。日本のクラシック音楽のコンサート会場でも、会場が盛り上がれば演奏者は踊っても構わないと私は思う。これからの時代には、楽しい演奏会づくりが欠かすことができない要素となろう。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2013年9月18日

書名: ヴェルディ ―オペラ変革者の素顔と作品―
著者:加藤浩子
発行日:2013年5月15日 初版第1刷
発行所:平凡社(平凡社新書)
目次:まえがき──「神話」や「伝説」からの脱出
序章 ヴェルディ、その「完璧」なる人生
[第一部 人間として作曲家として]
第1章 宿屋の息子──家系と家族
第2章 人生の同志──二番目の妻ジュゼッピーナ・ストレッポーニ
第3章 事業への意欲──農場主ヴェルディ
第4章 「憩いの家」と病院の建設──慈善家ヴェルディ
第5章 「建国の父」という神話──祖国統一運動とヴェルディ
第6章 「泣けるオペラ」の創造──作曲家ヴェルディ
第7章 作曲家の覇権の確立──劇場人ヴェルディ
[第二部 現代に生きるヴェルディ]
第8章 ヴェルディ上演の現在
第9章 今聴きたいヴェルディ歌手・指揮者
第10章 イタリア人名演奏家・芸術監督、ヴェルディを語る
[第三部 ヴェルディ全オペラ作品]
プレリュード──ヴェルディ・オペラの楽しみ方
第11章 群衆ドラマと心理劇の間で──前期作品 オベルト~レニャーノの戦い
第12章 メロディとドラマの融合──中期作品 ルイーザ・ミラー~ラ・トラヴィアータ
第13章 壮大なる葛藤──後期作品 シチリアの晩鐘~アイーダ
第14章 シェイクスピアが開いた新しい道──晩期作品 オテッロ~ファルスタッフ
第15章 オペラ以外の代表的作品 レクイエム~その他の作品
音楽用語解説
あとがき
ヴェルディ(1813年10年10日―1901年1月27日)は、今年(2013年)生誕100年を迎えた。そしてワーグナー(1813年5月22日―1883年2月13年)と同じ年に生まれたことは、この記念となる年になるまで、私は気づかなった。ヴェルディが87歳という天寿を全うしたのに対し、ワーグナーは、ヴェルディの半年ほど前に生まれ、69歳で世を去っている。ワーグナーは、ギリシャ悲劇に題材を求め、楽劇を創作し、現在の今でも毎年開催されるバイロイト音楽祭で何かと話題を振り撒いているので、比較的情報は入手しやすい。それに対してヴェルディは、我々日本人にお馴染のオペラ「椿姫」の作曲者であり、作品自体もメロドラマのような日常生活にテーマを取ったものが多く、ワーグナーより情報が入手しやすそうに見えるが、事実はその逆で、「ヴェルディって誰?」「どんな生涯を送ったか知っている?」と問われても、オペラファンでもない限り、なかなか簡単には答えられない。そこで1冊でヴェルディに関する全て、つまり、その生涯から、全作品までを網羅し、しかもコンパクトにまとまった書籍を探したのであるが、なかなかいい書籍が見つからず、焦っていたところ、書店で新書版のこの書、加藤浩子著「ヴェルディ―オペラ変革者の素顔と作品―」(平凡社新書)を見つけ、早速購入し読んでみた。新書版というと手軽に読めるイメージがあるが、この書は296ページもあり、ヴェルディの生涯から、1曲1曲の作品紹介まで網羅され、読み終わった印象は、1冊の単行本と変わりなかった。と言っても、読みやすさは文字通り新書並みであり、内容の深さについては単行本といったところが正解か。
全体は、3部構成となっている。「第一部 人間として作曲家として」はヴェルディの生涯がオペラを見るかのごとく語られ、一気に読み進めることができる。「第二部 現代に生きるヴェルディ」の「第9章 今聴きたいヴェルディ歌手・指揮者」では、現在のヴェルディのオペラが上演される際の代表的な歌手たちの寸評が載せられている。この辺は、単なる学者としての立場というより、ヴェルディの一オペラファンとしての著者:加藤浩子氏の経験が生きており、一人一人の歌手が生き生きと描かれている。続く、「第10章 イタリア人名演奏家・芸術監督、ヴェルディを語る」では、バリトン歌手のレオ・ヌッチ、指揮者のミケーレ・マリオッティ、それにフェニーチェ歌劇場芸術監督のフォルトゥナート・オルトンビーナの3氏に、筆者の加藤浩子氏が直接インタビューした記事が掲載されている。この部分は、差し詰め音楽ジャーナリストとしての活動の記録といったところか。そして最後の「第三部 ヴェルディ全オペラ作品」では、文字通りヴェルディの全オペラ作品が、あらすじ、聴きどころ、背景と特徴とが、それぞれコンパクトに紹介されており、辞書的な使い方もできるようにもなっている。これだけでも1冊の本になりそうな気もするほどである。この辺になると加藤浩子氏の編集者としての仕事のようにも感じられる。さらに、この後に1ページ半ながら「音楽用語辞典」が添えられているのがありがたい。よく聞く用語であるが、説明に窮することも少なくない。そんな時に便利なものだ。
つまり、この書の特徴は、新書版であるにも関わらず、1冊でヴェルディの全てが網羅されていることに尽きる。これ1冊読んでおけば、ヴェルディについて、いっぱしのことを言えるようになること請け合いだ。筆者の加藤浩子氏は、東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業、同大学大学院修了(音楽史専攻)。大学院在学中、オーストリア政府給費留学生としてインスブルック大学に留学。大学講師、音楽物書き。著作のほかに、オペラ、音楽ツアーの企画・同行も行う。普通、音楽家に関する書籍は、音楽学者や歴史学者が学術書のように執筆するか、あるいは入門者向けのものがほとんどだ。しかし、ある程度経験のあるクラシック音楽リスナーは、そのような書籍ではなかなか満足できないものだ。つまり、今活躍している演奏家の生の声や曲そのものの解説が欲しくなるが、そんな時に最適なのが、この書なのである。これは筆者の加藤浩子氏が、一音楽学者としてのほかに、ヴェルディの一ファンであり、さらに演奏家にも自らインタビューを行うとといった、マルチな才能に恵まれていることによるものなのであろう。
ところで、冒頭でヴェルディとワーグナーについて少し書いたが、ワーグナーがクラシック音楽家として並外れた波瀾万丈な人生(危険人物として国家から指名手配も受けている)を送ったのに対して、ヴェルディは、至極真っ当な市民生活を送った。それどころか、何百人の農夫を雇う大農場の農園主として経営者の顔を持つ上に、国会議員として政治家の顔も持っていたというから驚きだ。あれほどの中身の濃いオペラの作品を書くのですら、一人の人間が一生のうちに仕上げるには並大抵のことではない。これ以外に大農園主と政治家の仕事もこなしたというから、やはりヴェルディはただものではないのだ。さらに、ヴェルディは、慈善事業にも精を出し、数百人の上る貧民に施しをし、病院や、音楽家のための老人ホーム「憩いの家」など公共の施設にも出資している。音楽家のための老人ホーム「憩いの家」をヴェルディは「私の最高傑作」と呼んでいたという。このほか、作曲家のための著作権の確立にも尽力するなど、その八面六臂の活躍ぶりには唖然とさせられる。正にスーパーマンである。ヴェルディの死後、遺体が希望通り「憩いの家」の礼拝堂に移されたときには、盛大な国葬が執り行われた。あの大指揮者アルトゥーロ・トスカニーニのもと、スカラ座の合唱団が「行け、わが思いよ、黄金の翼に乗って」を歌い、20万人の人々が集まったという。この意味から、ヴェルディほど幸福な作曲家は、それまでも、そしてこれからもいないのかもしれない。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2013年7月03日
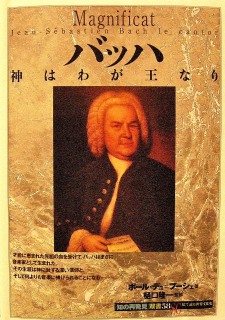
書名:バッハ―神はわが王なり―
著者:ポール・デュ=ブーシェ
訳者:高野 優
日本語監修:樋口隆一
発行所:創元社(「知の再発見」双書58)
発行日:2009年7月10日第1刷第7版発行
目次:第1章 音楽家の一族
第2章 若き音楽家の誕生
第3章 偉大なオルガニスト
第4章 ブランデンブルク協奏曲
第5章 トマス・カントル
第6章 音楽の捧げ物
資料編 バッハ、その人と音楽
ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685年―1750年)ほど、クラシック音楽界に貢献した作曲家は、その長い歴史を辿っても数えるほどしかいないであろう。それは時代を超えて、さらにはジャンルも越えて、現代においても大きな影響を及ぼしていることを見ても明らかだ。例えば、ジャズでバッハを演奏することだって、今や取り立てて言うことのほどの話になくなっている。つまり、バッハの音楽は時代を超えて、普遍的な音楽のエキスのようなものを我々に与え続けている。そんなバッハも、一時期その存在が完全に忘れ去られた時代もあったというから、びっくりさせられる。同じような事例は、最近の日本画界にもある。一時忘れ去られていた伊藤若冲が今や時代の寵児となって、多くの人から賞賛を浴びている。バッハは、世俗的カンタータは作曲したが、オペラは作曲しなかった。大衆が最も身近に感じられる音楽がオペラであり、バッハのように宗教曲が多く、宗教曲以外の曲でも抽象的な曲がほとんどの作曲家は、当時は一般的な人気が続かなかったのであろう。ところが、このことが逆に幸いして、死後250年以上経った現在、人々に大きな影響を与えているということが言える。
ということで大バッハのことが知りたくなり、音楽の専門家ではない一般の人が気楽に読めるバッハの本を探してみると、これがなかなか良い本が見当たらないのである。音楽学者が書いた本は、2~3ページ読むとたちまち頭が痛くなるし、普通のクラシック音楽ファンには、その高度の音楽理論は難しすぎるケースがほとんどだ。バッハという作曲家はどんな人生を送った人なのであろうか、当時はどんな評価を受けていたのか、バッハは何故偉大な作曲家と言われるのだろうか、などなど素朴な疑問に答えてくれる本はないものか、と探してみると・・・あったのがこの「バッハ―神はわが王なり―」(ポール・デュ=ブーシェ著/高野 優訳/樋口隆一日本語監修/創元社刊<「知の再発見」双書58>)である。どこが取っ付き易いのかというと、カラフルな絵画の豊富さに、まず感心させられる。250年以上も前のドイツでの話なので、我々日本人にとっては、なかなかイメージがが湧かない。この書は、カラフルな絵とその解説文を読むだけでも、当時の音楽状況が目の前に自然に現れてくるようでもある。そして、それらのレイアウトも教科書的でなく親しめる。何か絵本でも読んでいるかのような気分にもさせられる。
この本の本文の文章自体も、通常の翻訳本以上の高い質が感じられる。つまり、訳者に加え、日本語監修者が、日本語の訳文を、さらに音楽的見地から推敲してあるので、難解な個所はほとんどなく、素人でもすらすらと読み進めることができるのだ。ところで、バッハは、一体どんな人だったかをこの本から探ってみると・・・、意外にも人間味あふれる普通の人だったことが判明する。我々がイメージするバッハ像は、小学校の音楽室に飾られたあの厳格な顔をしたバッハなので、さぞや音楽一筋で謹厳実直を絵で描いたような人生を送ったかと思いきや、どうもそうでもなさそうなのである。例えば、「アルンシュタットにいた頃、バッハは訓練を任されていた合唱隊の質の低さに苛立ち、ファゴットを担当していたガイエルシバッハというラテン語学校の生徒に『おまえのファゴットは年取った山羊のようだ』と言ったことがあった」、その後「バッハが自宅に戻る途中、城を出てマルクト広場にさしかかったところで、6人の生徒たちがいるのを見た。その中の一人ガイエルシバッハが、バッハの後を付けてきて、どうして自分を侮辱したのか、と叫びながらバッハに殴りかかった」、そして「バッハは思わず剣に手を掛けた。ガイエルシバッハはバッハの腕をつかみ、乱闘が始まった」。これは、夏目漱石の「坊ちゃん」そのものではないか。私は、これを読んでバッハが一挙に身近な存在になった。
この本の巻末に掲載されている「資料編」も、本文に負けないくらいの充実している。それらは①歴史の中のバッハ②バッハ家の系譜③素顔の天才④バッハの手紙⑤演奏することと教えること⑥音楽におけるバイブル⑦宗教作品⑧数の神秘⑨バッハが遺したもの―からなっている。上記の喧嘩のエピソードも③素顔の天才から引用したもの。②バッハ家の系譜では、バッハ家の一人一人の素顔が描かれて誠に興味深い。ところで、この本は、創元社が1990年に創刊した叢書「知の再発見」双書の中の1冊である。「知の再発見」双書は、創元社がフランス・ガリマール社と提携し、フランス・ガリマール社が発刊している「ガリマール発見叢書」をベースとした訳書シリーズである。正確さを期すため、訳者以外に日本人専門家による監修が行われており、さらに図版が多く掲載されているのも特徴。装丁は、戸田ツトム氏と岡孝治氏が担当し、日本の書籍としてレイアウトの斬新さを打ち出すことにも成功している。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2013年4月29日
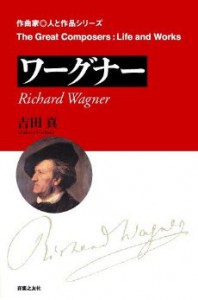
書名:ワーグナー ~作曲家◎人と作品シリーズ~
著者:吉田 真
発行所:音楽之友社
発行日:2005年1月5日第1刷発行
目次:<生涯篇>
演劇少年──ライプツィヒとドレスデン(1813~1833)
新米指揮者──ヴュルツブルク、マクデブルク、リガ(1833~1839)
野心家──パリ(1839~1842)
宮廷楽長──ドレスデン(1842~1849)
おたずね者──チューリヒ(1849~1858)
逃亡者──ヴェネツィア、パリ、ビーブリヒ、ウィーン(1858~1864)
王の賓客──ミュンヘン、トリープシェン(1864~1871)
祝祭の演出者──バイロイト(1871~1879)
巨匠──ヴェネツィア(1880~1883)
補章 その後のワーグナー家とバイロイト祝祭
<作品篇>
1.《さまよえるオランダ人》
2.《タンホイザーとヴァルトブルクの歌合戦》
3.《ローエングリン》
4.《トリスタンとイゾルデ》
5.《ニュルンベルクのマイスタージンガー》
6.《ニーベルングの指環》:《ラインの黄金》《ヴァルキューレ》《ジークフリート》《神々の黄昏》
7.《パルジファル》
<資料編>
作品一覧
ワーグナー年譜
今年はワーグナー(1813年~1883年)の生誕200年に当たる年なので、ワーグナーについての書籍を読みたいと思って探してみると、あるわ、あるわ、ワーグナーについての書籍は、膨大にあり、一説によると一人の人物の書籍の種類では、ゲーテに次いで世界第2位になるのだという。書店で見てみると、流石にそう多くは置かれてはないが、それでも、その置かれた書籍は、あたかも学術論文みたいに、ちょっと見ても目がくらくらするほど難解な内容であることが分かる。そう言えば、ワーグナーは、ショーペンハウエルに憧れ、ニーチェとも親交を結ぶ(後にニーチェの方がワーグナーから去って行った)など、晩年に向かうほどその歌劇(楽劇)の内容は、深遠なものとなり、一筋縄ではいかない難物であるのだから、その書籍が難解になるのはしょうがないとは思うのだが・・・。そこで、この際は、ワーグナーという人物を理解でき、ついでにその作品の概略が簡単に解説してある書籍はないものかと、さんざん探してみた結果、最後に行き着いたのが、この「ワーグナー ~作曲家◎人と作品シリーズ~」(吉田 真著/音楽の友社)であった。
一部の熱烈なワグネリアンならともかく、一般の日本人のリスナーにとって、ワーグナーという作曲家の名前は知っていても、その歌劇(楽劇)の内容を理解することは難しいし、まして、その話のストーリーがどうなっているは、分からずじまいであることがほとんどであろう。このことは、第二次世界大戦という歴史の重みも大いに重なってくる。第二次世界大戦後の日本は、反戦平和が国是みたいになっていたわけで、ワーグナーはナチスドイツが、国家意識の発揚に利用したということもあり、どうもしっくりと耳に馴染まなかったという不幸な歴史的背景もあった。それと、今でこそ、ワーグナーの作品は、人気テノールのフォークトなどが来日して、本場の雰囲気で聴く機会も多くなったが、昔はそう簡単にワーグナーの作品を生で聴くチャンスはなかった。ショルティなどが演奏したレコードも話題となったこともあったが、レコードでは、今なら当たり前になった日本語の字幕を見ることができず、そのストーリーを追うには、活字で読むという努力を必要とした。そんなこんなで、その名は広くが知られているワーグナーではあるが、現在、その人物像および作品内容の理解が十分に浸透しているとは言い難いのではなかろうか。何しろ、ドイツのバイエルン州で毎年行われるバイロイト音楽祭に申し込んでも10年待たねばチケットを入手できないというのだから(小泉元首相はバイロイトに聴きに行ったそうであるが、10年待ったというより、やはり首相特権だったのでしょうね)。
そんな時に役立つのがこの本だ。ワーグナーの生い立ちから、どのような経緯で後年の歌劇(楽劇)の作曲に至ったのかが、誰でも分かる文章で、年代を追って書かれている。そのため、読者はまるでワーグナーの時代にタイムスリップしたかのように、ワーグナーのごく真近で、刻々と変わるワーグナーの運命を目の当たりにすることができるのだ。ワーグナーが何故、歌劇(楽劇)にのめり込んでいったのか。この本でも書かれているが、やはりベートーヴェンの存在が大きいことが推測される。ワーグナーも初期の頃、交響曲を1曲書き、2曲目は、未完に終わっている。もし、ベートーヴェンが交響曲を作曲せず、歌劇の名作を大量に生み出していたら、ワーグナーは歌劇には目もくれず、交響曲の作曲に没頭したのではなかろうか。この本から感じられるワーグナーの性格からすると、そんなことも感じさせてくれる。ワーグナーは、もともとプロレスタントであり、当時の国王からは、革命家として跡を狙われてもいたことなどもこの本で紹介されている。つまり、ワーグナーは、ナチスドイツが勝手につくり上げたような国粋主義者ではなく、ヨーロッパ人の心の拠り所としてぃた古代ギリシャ精神への回帰という精神面が大きかったのだ。
この本は、全体が生涯編、作品編、それに資料編の3つに分けられている。生涯編は、生まれてから死ぬまでのワーグナーが辿った作曲家人生に関して、誰にでも理解できる平易な文章で綴られており、一気に読み進むことができる。特に、ワーグナーが死んだ後から現在に至るまでの経緯が「補章 その後のワーグナー家とバイロイト祝祭」としてまとめられているので、現在とのつながりが理解できて便利だ。読み終わってみると、これまで遠くに感じられたワーグナーの音楽が、ぐんと身近に感じられるから不思議だ。このため、ワーグナーの食わず嫌いなリスナーにとっては、ワーグナー生誕200年に当たる今年、是非読んでほしい本であるし、一方、熱烈なワグネリアンには、ワーグナーの一生についての恰好のおさらいのための書物となろう。次の作品編は、ワグナーをこれから知りたいリスナーにとっては誠にありがたいページだ。というのは、たった、42ページに「さまよえるオランダ人」から「パルジファル」までの11作品のあらすじが、コンパクトに紹介されているからだ。これだけ読めばワーグナーの作品について、いっぱしのことは言えるようになること請け合いだ。そして、最後にワーグナーの作品一覧と年譜が付けられている。ワーグナーというと、何か難しくてとっつきにくいと感じているリスナーにとっては、これ以上の書物はないであろう。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2013年3月07日

書名:人生が深まるクラシック音楽入門
著者:伊東 乾
発行:幻冬舎
目次:序章 クラシック音楽のある生活
第1章 クラシック音楽とは何か
第2章 美しい響きを創造する~西洋音楽の歴史<バロック・古典派篇>
第3章 キリスト教からの解放~西洋音楽の歴史<ロマン派・国民楽派篇>
第4章 レコーディング時代の音楽とは~西洋音楽の歴史<印象派から現代音楽へ>
第5章 楽器のあんな歴史、こんな音色~オーケスト編成と器楽法
第6章 音楽、どこで聴きますか~生演奏と録音の話
第7章 音楽は誰が作るのか~指揮者と演奏者の話
終章 歌うクラシックのススメ
クラシック音楽リスナー入門者にとって大切なことの一つは、順序立てて聴くこと。易しい曲、短い曲から聴き始めて、徐々に難しい曲、長い曲に向かうと、スムーズにクラシック音楽ライフをエンジョイすることができる。これは、絵画でも同じことが言えるのではないか。いきなり、ピカソの絵を見せられ、「ピカソは偉い絵描きだ。何処がいいのか言ってみろ」と言われても、多くの人は困惑する。心に中では「ピカソの絵が何処がいいのかさっぱりわからない」と思っても、口に出しては言わないだけだ。ピカソの描く絵は何故ああなったのかは、美術史の長い歴史を振り返って、その時代々の背景を探っていくと徐々に分かってくるのだ。ローマ・カトリック時代の絵とプロテスタント時代の絵はおのずと違う。ルネサンス時代とバロック時代の絵も違う。印象派の時代の絵は、我々にはお馴染みで、誰でも分かると思うが、もし、ローマ・カトリック時代に生きた人が印象派の絵を見たら多分「あんなぼんやりとした輪郭の絵の何処がいいか分からない」と思うのではなかろうか。そんなわけで、クラシック音楽の歴史を振り返り、その時代に流行った音楽を聴き、現代まで辿るのが、クラシック音楽を理解する一番の早道だ。
これまでクラシック音楽史の本は無数に発行されているし、楽聖物語みたいな読み物も数多い。しかし、いずれも、クラシック音楽リスナーからすると“欠点”を持っているのだ。多くのクラシック音楽史の本は、音楽学校の学生が学ぶにはいいだろうが、リスナーからすると、無味乾燥な部分が多く、さらに難解な記述も少なくない。一方、楽聖物語的な本は、「ベートーヴェンが月の光を見て、月光ソナタを作曲した」的な記述が多く、つい「それがどうした」と言いたくなってしまう。リスナーが知りたいのは、「現代音楽って聴いてほんとにいい曲と思うの」という答えだ。ピカソの絵と同じに「あなたは、シェーンベルクの音楽を聴いて感動するのですか」と問うてみたいし、「感動する」という人に、シェーンベルクのどこがいいのかの解説も聞きたい。こんな観点からクラシック音楽の解説書を探してみると、ほとんどない。何故か、ないのである。これでは、健全なクラシック音楽リスナーは育つはずはない。健全なクラシック音楽リスナーが育たなければ、日本のクラシック音楽界も発展しない。こんなことを考えてたところに「人生が深まるクラシック音楽入門」(伊東 乾著/幻冬舎刊)を見つけ、読んでみた。
この本は、クラシック音楽の入門者向けの本ではあるが、通常の入門者向けの本とは少々違う。楽理の解説本でもなければ、作曲家のこぼれ話の本でもない。クラシック音楽を歴史に沿って書いてあるのではあるが、何故その時、こういう音楽が生み出されたのかが平易にかいてあるのだ。例えば、「『古典』音楽の中に『古典派』がある?あらためて考えると不思議ですね」と書いてある。確かに、クラシック音楽は古典音楽であり、その中の古典派ってなんだ、と問えわれると答えに窮する。ここから古典派の名付け親の追跡が始まる。このような筋道でクラシック音楽を解説してもらえると、クラシック音楽リスナーは、苦も無く、これまで恥ずかしくて誰にも訊けなかった疑問の答えに行きつくことができるのだ。今、書店には「今さら訊けない・・・」という本が多いが、この「人生が深まるクラシック音楽入門」は、さしずめクラシック音楽版「今さら訊けない本」なのかもしれない。つまり、入門者向けに書かれていても、実は、クラシック音楽通を自認するあなたが、こっそりと読む本なのかもしれないのだ。
この本の特徴は、「古典派」のような、分かっているようでも、実は分かっていないテーマの解説が随所に出てくることだ。「ゴシック建築の教会は、あまりにも広くて天井が高いので、それまでのロマネスク建築ほど声が響きません。風呂場で単旋律を『あ~』と唸っていたら、いきなりドーム球場のど真ん中引っ張り出されたとでも思ってください」とある。何のことだと読み進むと、このことが、「人工的なエコーづくり」に繋がり、ポリフォニー音楽へと発達を遂げたというのだ。通常のクラシックの音楽の本には、モノフォニーとポリフォニーの話は出てくるが、それが何故生み出されたかは書いていない。実はその背景には建築技術の発達が隠されていたのである。これならよく分かる。この本は、筆者による口述筆記を原稿にしたもであり、通常の書籍とは少々異なるかもしれない。例えば、分量が多い(新書版で267ページ)ので、全てをそう簡単には読み終えることができない。まあ、何回かに分けて、講演会でも聞いている気分で読めばいいと思う。巻末に付いている「50年楽しめるリスニングガイド」(「是非ライブで聴いてほしい作品12曲」「録音でも味わい深い作品127曲」)は、大いに参考になる。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »