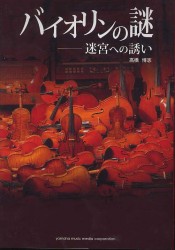2013年1月23日

書名:指揮者の役割~ヨーロッパ三大オーケストラ物語~
著者:中野 雄
発行:新潮社(新潮選書)
目次:序章 指揮者の四つの条件
第1章 指揮者なんて要らない?――ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
第2章 カラヤンという時代――ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
第3章 オーケストラが担う一国の文化――ロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団・アムステルダム
終章 良い指揮者はどんな指示を出すのか?
オーケストラは、その国の民族的性格をかなり忠実に表現しており、聴いていて興味が尽きない。最近私が体験したケースで印象に残るのは、パーヴォ・ヤルヴィ指揮のフランクフルト放送交響楽団の演奏会であった。当日は、ヒラリー・ハーンのヴァイオリン演奏でメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲とブルックナーの交響曲第8番が演奏された。パーヴォ・ヤルヴィ指揮フランクフルト放送交響楽団の演奏は、ブルックナーに正面から取り組み、一部の隙もない緻密な演奏であった。同時に強烈なエネルギーの発散みたいなオーケストラの咆哮を久しぶりに聴くことができた。で、問題は演奏そのものでなく、オーケストラメンバーが席を立つ時と、席に座る時のタイミングである。フランクフルト放送交響楽団のメンバー全員は、誰の指示でもなく、この立つ時と座る時のタイミングが、全員ぴたりと一致するのである。まさか、練習しているわけでもないだろうから、この全員一致は国民性の現れではなかろうかと思わざるを得ない。
では、日本のオーケストラはどうか。これはもう演奏中の熱中度は世界一と思わせるような、全員の頑張りの姿勢が特に目立つのだ。これも“国民全員一致してことに当たる”といった日本の国民性の現れではなかろうか。一方、オーケストラの聴衆についても、国民性が現れる。欧米の演奏会の録音放送などを聴くと、演奏が終わり、一拍おいてから小さな拍手で始まり、それが徐々に大きくなって行く。一方、日本の聴衆はというと、演奏が終わるか終らないうちに拍手が始まり、しかもそれが最初から大きな拍手なのだ。これは、日本人がせっかちな国民性である、ということを現しているのであろうか?
この「指揮者の役割~ヨーロッパ三大オーケストラ物語~」(中野 雄著/新潮選書)は、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、それにロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団というヨーロッパを代表する3つのオーケストラを取り上げ、それぞれの楽団の歴史から始まり、これまで活躍してきた指揮者、楽団員を浮き彫りすることにより、そのオーケストラの特徴を読者の前に赤裸々に提示する。同書が他書と異なる点は、当時現役として、それぞれのオーケストラを引っ張ってきた楽団員たちに、直接筆者がインタビューしている点である。つまり、貴重な歴史的証言が満載され、それぞれのオーケストラの貴重な歴史書にもなっている。このことは、現在においても、これらのオーケストラの演奏を聴く際に、大いに参考になると言っても、過言なかろう。
指揮者が、「巨匠(マエストロ)」と呼ばれて、その生涯を全うするための資質として、著者の中野 雄氏は、次の4点を挙げる。第一は、強烈な集団統率力、第二は、継続的な学習能力、第三は、巧みな経営能力、第四は、天職と人生に対する執念、の4つである。つまり、この書に登場する、歴史に名を残す大指揮者達は、これらの4つの資質を兼ね備えているということになる。一方、大指揮者に“仕える”楽団員の方はどうであろう。ウィーン・フィルのコンサートマスターを務めたライナー・キュッヒル氏が「良い指揮者とは、私たちの音楽を邪魔しない指揮者のことをいいます」と言ったということが紹介されている。この一言の中に、ウィーン・フィルの楽団員のプライドが込められているようで、思わず読みながら唸った。言い方を変えれば「我々をコントロールできると思うなら、やってみな」と言ってるのに等しい。そんなウイーン・フィルの楽団員達をフルトヴェングラー以降の指揮者がどうコントロールしていったのかは、読んでみてのお楽しみ。
ベルリン・フィルについては、カラヤンとの出会いと葛藤とが詳細に記載されており、現在でもベルリン・フィルの演奏を聴く際には是非とも知っておきたい内容である。ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団については、筆者と50年来の付き合いというコンサートマスターだったヘルマン・クレッパース氏の貴重な証言により、メンゲルベルクから引き継いだ指揮者のベイヌムの人間像が明らかにされる。いずれにしてもこの書は、ヨーロッパ三大オーケストラを通して熱く語った、著者のクラシック音楽に対する愛着がひしひしと伝わってくる力作である。
(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2012年9月26日

書名:ピアノはなぜ黒いのか
著者:斎藤信哉
発行:幻冬舎
目次:第1章 ピアノはなぜ黒いのか
第2章 世界一ピアノをつくっている国
第3章 こんなに大きな音は必要か
第4章 日本のピアノづくり100年
第5章 ヨーロッパのピアノの魅力
第6章 ピアノを調律するということ
第7章 ホームコンサートをしてみよう
ピアノは、ヴァイオリンと並びクラシック音楽を象徴する楽器として親しまれている。しかし、あまりにも身近にある楽器であるが故に、一般の人は、意外にピアノの基礎知識がないことに気づく。そんな状況の下でこの「ピアノはなぜ黒いのか」(斎藤信哉著/幻冬舎新書)を手に取り、タイトルである「ピアノはなぜ黒いのか」を眺めてみると、一瞬ぎくっとなるのである。「なぜ黒いのか言ってみろ」と言われたって、「ピアノの色は昔から黒いから、今でも黒いのが当たり前」ととしか言いようがないである。この本は、読む前からタイトルだけで“筆者の勝”といった趣がある本であり、後はただただ、その真相を知るために読み進むことになる。「ヨーロッパやアメリカ、あるいはそれ以外のほとんどの国では、ピアノといえば木目が当たり前になっているのです。エッ、ウッソーと思う方は、インターネットなどで各国の写真をごらんください。私の言っていることが、ウソでないことがお分かりいただけるはずです」。でここまで読んで、でもおかしい。テレビで海外のコンサートを見ると、黒いピアノを使っているではないか。「木目のピアノを使った海外のコンサートなんて見たことないぞ」と反論したくなる。しかし、いくら抵抗したって無駄だ。「ステージの上の主役はあくまでピアニストです。ピアノはけっして主役ではありませんから、そのピアノが目立ってはならないから黒いピアノを使うのです」と軽くかわされてしまう。ここで私みたいな読者は、筆者に対し完全敗北を喫し、後は奴隷のごとくひたすら読み進む。
日本に最初にピアノが持ち込まれたのは、江戸時代も終わりに近い、いまから180年ほど前の1823年(文政6年)だった。持ち込んだのはシーボルト。それは、高さ90センチほどのテーブル状の形をしており、外装は黒塗りではなく、マホガニーという木。うーん、やはり黒塗りではなかったことがこれで証明されてしまった。現物は山口県萩市にあるというから見てみたい。では、国産第1号のピアノは、いつつくられたのであろうか。ドイツ人技術者の指導の下、輸入材料を使ってつくったのが西川ピアノで1880年代の終わりごろという。純国産はというと、1900年に山葉(ヤマハ)がつくったもので、当時のお金にして1000万円もしたという。この頃の外装はというと、既に日本独自の取り組みとして黒が使われていたらしい。これは何故なのか。原因は日本の湿気を避けるため黒の漆を外装の表面に塗ったというのが、ことの真相らしい。さらに、黒の外装の方が安くつくれたことも、日本で黒のピアノが普及した理由という。逆にヨーロッパでは木目の上から黒を塗るため、黒の方が木目仕上げより高くついてしまう。
この本を読み進めていくと、色だけでなく、ピアノのメーカーについても、素人の常識はあっさり覆されてしまう。まず、日本で「ピアノメーカーは?」と問われれば、誰もが「ヤマハ、カワイ」は答えられても、次がなかなか出てこない。ところが、この本の巻末資料として「日本のピアノブランド(機種)一覧」が8ページにわたって掲載されているが、この中に我々が聞いたこともないピアノメーカーがたくさんあることに驚かされる。現在、世界には数百のピアノメーカーと数千のピアノブランドが存在しているといわれている。しかし、その多くが消え去った結果のことだという。オーストリアのウィーンには、かつて100を超えるピアノメーカーが存在していたが、その中で現在残っているのがたった1社だけだというから驚きだ。ヨーロッパのピアノメーカーは、1台1台手づくりで作業を行うため、小規模経営のところがほとんどで、このため長くは、生き残れないのであろうか。
そして、次なる驚きは、現在、世界で最も多くピアノを生産している国の話だ。楽器業界に通じている人は直ぐ分るかもしれないが、素人には分からない。やはり、日本かと思っていたら、中国であった。日本のピアノ生産台数は、最盛期は年間39万台であったそうであるが、現在の中国は既にそれを超え、年間40万台を突破しているという。中国は世界の工場としてGDPで日本を抜いたが、ピアノ生産でも世界一の座を獲得していたとは・・・何ともはやといった感じだ。しかし、この本では筆者の斎藤信哉氏が中国のピアノメーカーを訪問した時のレポートが掲載されており、なかなか興味深い。つまり、世界一はあくまで生産台数のことであって“質”のことではないのである。かつて、日本のピアノメーカーは、ヨーロッパを抑え、生産量世界一に輝いた時期があった。これは、日本のメーカーが木材の自動乾燥化の技術を独自に開発したからであり、ヨーロッパのピアノメーカーを質で追い抜いたということではなかった。この辺も専門家には分かって、我々部外者にはなかなか理解がいかないところだ。この本は、そんなピアノメーカーの舞台裏も垣間見させてくれる。さらに、ヨーロッパのピアノメーカー1社、1社を取り上げ、その製品の特長を解説した件は、読んでいて「なるほど、そうだったんだ」と納得がいく。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2012年6月28日
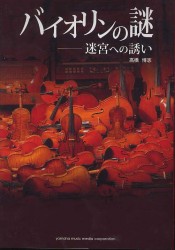
書名:バイオリンの謎~迷宮への誘い~
著者:高橋博志
発行:ヤマハミュージックメディア
目次:第1章 「名器」とはなにか?
第2章 謎に包まれたストラディヴァリの生涯
第3章 バイオリンの歴史は謎ばかり
第4章 名バイオリニストと大作曲家をめぐるミステリー
バイオリンは、人間臭い楽器だ。オーボエなども人間臭い楽器なのだが、何といってもバイオリンは、その出番で他の楽器を大きくリードするから、人間臭い楽器の右代表と言っても文句はなかろう。ピアノなどになると、人間臭さは大きく後退して、機械的な美しい音色に聴き入ったり、まるで打楽器のように大きく、金属的な響きにびっくり仰天することも少なくない。ピアノは、演奏家が機械というものをいかに手なずけ、そしてその機械を身近な楽器に仕立て上げるのかを競っているかのようでもある。
それに比べ、バイオリンは、演奏家の体の一部のようでもあり、演奏家の分身のようでもある。バイオリン一挺を如何に力を入れてもそれほど大きな音は発しない。その代わり、バイオリンの達人が弾く、微妙なニュアンスを持った音色を聴くと、人が発する声のようでもあり、声にならない心の叫びのようでもある。オーケストラの配置を見ても、指揮者の回りにバイオリンなどの弦楽器があり、後ろのほうに管楽器や打楽器が置かれる。その弦楽器の中でも女王の地位にあるのがバイオリンである。
しかし、そんなバイオリンではあるが、私のようなクラシック音楽のリスナーがどれほどバイオリンのことを知っているかと訊かれると、はたと返答に窮してしまう。バイオリンは、いつ頃、誰によってつくられ、今日の形に落ち着いたのか。“ストラディヴァリ”の名前だけは知っていても、いつ頃の人で、何故“ストラディヴァリ”が飛び抜けて有名なのかを、そもそも知らない。そんな人のために最適なバイオリンの歴史を解説してくれる本が登場した。それが高橋博志著「バイオリンの謎―迷宮への誘い」(ヤマハミュージックメディア刊)である。
バイオリンの本と聞くと、バイオリンの弾き方の教科書か、あるいは、難しい楽典の解説書かな、とつい尻込みをしてしまうが、この本はそうではない。極端な話、バイオリンも知らないし、クラシック音楽も知らない・・・人だって、歴史ファンなら誰でも最後まで面白く読み通すことができる。つまり、この本は、ストラディヴァリという天才バイオリン製作者を軸にした一種の“推理小説”と思えばいい。何故“推理小説”なのかというと、ストラディヴァリという人自体が謎の人物であり、何故ストラディヴァリが作製したバイオリンが名器と言われるのかも、現在でも完全には解明なされていないからである。
それでは、最初の疑問である、バイオリンは誰が最初に製作したのか。同書によると候補は、アンドレア・アマティ、ガスパロ・ダ・サロ、カスパール・ティーフェンブルッカーの3人に絞られるが、最終的には、イタリアのクレナモでバイオリン製作をしていたアンドレア・アマティ(1505年以前―1580年以前)だろうということになる。しかし、著者の高橋博志氏によると「アマティが一人でバイオリンを発明したということではない。独創的なアイデアを持った人物からヒントを得て完成させた」のでは、と推測する。いずれにせよ、バイオリンは、徐々に形を進化させて作り上げられたという楽器ではなく、短い年月に間に一気に完成を見た、極めて異例な楽器であるのだという。
そして、現存する「最古のバイオリン」とは、というと1560年代の作品なのだそうだ。一方、絵画に描かれた最古のバイオリンはというと、北イタリアのヴェルチェッリという町の教会に「オレンジの聖母マリア」という絵画があり、そこにバイオリンに似た楽器を弾く天使が描かれている。この壁画が描かれたのは1529年で、これが、バイオリンに直接つながる楽器の最古の絵画資料であるとされている。なるほど、なるほど、これでバイオリンの謎は大分解けたぞ、と思うのは早計だ。
ここからがこの本の核心に入っていくことになる。イタリアのクレナモで活躍した天才バイオリン製作者のアントニオ・ストラディヴァリの登場である。いよいよ真打の登場ということになる。生涯に制作した楽器の数は、バイオリンだけでも1000挺(現在残っているのは600挺ほど)を超えるといわれており、このほかに、ビオラやチェロも製作し、これらは皆、現在最高の楽器と高く評価されているのである。ここからが謎の始まりとなる。ストラディヴァリが何時、誰の子として生まれたのがどうもはっきりとしない。
また、よくストラディヴァリは、アマティの弟子ということが言われているが、高橋博志氏によると「ストラディヴァリは、正式な弟子でなかったばかりか、アマティの工房にいたという記録も、何ひとつ残っていない」そうなのである。ここからが謎解きが始まるので、その全貌は同書で直接お確かめ願いたい。さらに同書の最後の章には「名バイオリニストと大作曲家をめぐるミステリー」が収められているが、ここには名バイオリニストたちのバイオリンに纏わる逸話が紹介されており、これまた興味津々。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2012年3月30日

書名:西洋音楽論~クラシックに狂気を聴け~
著者:森本恭正
発行:光文社(光文社新書)
目次:第1章 本当はアフタービートだったクラシック音楽
第2章 革命と音楽
第3章 撓む音楽
第4章 音楽の右左
第5章 クラシック音楽の行方
第6章 音楽と政治
森本恭正著「西洋音楽論ークラシックに狂気を聴けー」(光文社新書)は、これまで我々が漠然と「当たり前」と考えて、特別考えてもみなかったクラシック音楽についての“常識”を、根本に遡って考え直している、貴重な書籍である。「本当はアフタービートだったクラシック音楽」という中見出しを見ると、「アフタービート云々なんて言うのは、ジャズやロックの音楽のことで、クラシック音楽のことではないのではないか」という違和感がたちまち芽生える。アフタービート(この言葉自体は和製英語だそうで、正確な英語はアップビート)とは、例えば2拍子の後拍を強く叩くことであり、ジャズやロックではお馴染みのこと。
しかし、ベートーヴェンも2拍目を強調することによって、曲を前へまえへと進めて曲を書いた。これすなわちスウィングであると。スウィングなんて言葉を聞くと 私などは反射的にスウィングジャズを思い浮かべるが、ベートーヴェンがスウィングしていたなんて、 思わず「何てことを言い出すのだ」と読みながら思わず考え込んでしまった。しかし、読み進むうちに、このことが西洋音楽の本質に迫ることが徐々に解明されていく。
ベートーヴェンの有名な交響曲第5番「運命」の出だしは、「タタタターン」ではなく、「『ン』 タタタターン」である。これはアフタービート以外の何物でもないという。「当時のヨーロッパの聴衆には、この強烈なアフタービートを受け入れる土壌があった」と。当時の聴衆は、ベートーヴェンが作曲した新曲のアフタービートに反応し、それがもたらすスイング感に熱狂した、というわけだ。現在のクラシック音楽の聴衆が果たして同じように「運命」を聴くことができるのか。今の聴衆は「運命」と聞いただけで、「運命の扉はかく叩かれる」のような哲学的思考で頭がいっぱいになり、ベートーヴェンが編み出した革命的なアフタービートもスウィング感も感じようともしくなってし まっているのではないか。
要するにクラシック音楽もジャズもロックも、視点を変えてみれば思わぬ共通点が見つかるのかもしれない。前から指摘されている通り、ジャズとバロック音楽には共通点があるといわれる。共に通奏低音の上に音楽が進行するスタイルだというのである。こう考えてみると、クラシック音楽だ、ジャズだ、ロックだとジャンル分けして互いにそっぽを向いているのは、 意外に滑稽なことなのかもしれない。
この書、森本恭正著「西洋音楽論ークラシックに狂気を聴けー」(光文社新書)のユニークな点は、幾つか挙げられるが、その一つは、クラシック音楽と民族音楽の違いを曖昧にせず、明白に浮き彫り にしている点だろう。「五線譜は、私が、半分冗談でしかし、内実100%本気で言った通り、 EUROPEAN UNION NOTATIONなのだ。即ち、ヨーロッパ言語を基盤にしている人々に『共通な』表記法なのである」「ヨーロッパ音楽はヨーロッパ言語を基盤にしているが故に、ヨーロッパ音楽は全て基本的にアフタービートだと思っていただきたい」。
それに対して、邦楽は、「太夫達の謡も篠笛も、奏でられているのは節であって、旋律ではない。求められているのは、微妙な音程のずれから生じる音色で、ハーモニーではないのだ。だから西洋的な音程という概念そのものがあてはまらい」のであると。つまり2つの音楽は、全く違ったものだと指摘する。西洋音楽には指揮者がいるが(階級的組織)、邦楽や他の民族音楽にはそんなものは存在しない。西洋音楽は、曖昧さや雑音を排除した結果、世界を制覇したわけだが、現代音楽になり、逆に雑音を取り込み、西洋音楽の限界の突破口を切り開こうと試みた。
この書の最後で、森本はベートーヴェンの「第九交響曲」を取り上げる。「殆どの全作品を通じてアフタービートで書いたベートーヴェンが、この彼をして最大の交響曲の終楽章で、オン・ザ・ビートの音楽を書いたのだ。卑近な例だが、私達日本人には阿波踊りのビートを連想させる、ターンタタンタ、という個所を思い出して戴いたら良いだろう。それは正しく東洋由来のものだ」とベートーヴェンをして西洋音楽の限界を予言していたのだという。森本は西洋音楽のこれまでの優位性は認める一方、その限界 にも言及する。西洋音楽(クラシック音楽)一辺倒になる危険性をこの書から少しでも感じ取ることが 出来たら、筆者は「してやったり」と感じるのではなかろうか。
それにしても、邦楽がもっと我々の身近な存在になれば、また新しい視点が広がるような気もするのだが・・・。この書は、我々にとって“当たり前”の存在になっているクラシック音楽を、ゼロから見つめ直すのに格好の書ではある。 (蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2011年9月07日

書名:モーツァルトを「造った」男~ケッヘルと同時代のウィーン~
著者:小宮正安
発行:講談社(講談社現代新書)
目次:プロローグ 「凡庸」の人
第1章 1800年の男
第2章 青春ビーダーマイアー
第3章 ディレッタントという生きかた
第4章 愛国の音楽
第5章 ザルツブルクの日々
第6章 活ける像の創造
第7章 作品目録誕生
第8章 「神」をめぐる駆け引き
第9章 帝国の音楽
第10章 その後の「ケッヘル」
エピローグ 「惑星」の力
モーツァルトの曲目が紹介されている個所に必ず表記されているのがK(ケッヘル)という番号である。モーツァルトの作品には必ず付いているので、通常当たり前のこととして、このケッヘル番号だけが話題になることは滅多に無い。そうなるとケッヘルとは何かということを、改めて切り出すことは、何か気恥ずかしくて人に言えない。そうなると、ますます話題になることも無くなり、ケッヘルとは何かという謎が残ったまま、いつまで経ってもすっきりしない。
そんな中、「ケッヘルとは人の名さ」と誰か言うと、皆は「そうだそうだ、モーツァルトの作品に通し番号を付けた昔の人の名だ」ということになって、ここでもそれで一件落着してしまう。ケッヘル、つまりルートヴィヒ・フォン・ケッヘル(1800年-1877年)という人は、どんな人で、何故モーツァルトの作品に通し番号を付けたのか、という根源的な謎は残ったままになるのだ。そんな謎を解き明かしてくれる本が「モーツァルトを『造った』男」(小宮正安著)なのである。
では「モーツァルトを『造った』男」の「造った」とはどういう意味なのであろうか。筆者は次のように解説する。「日本語では“つくる”という意味に対し、いくつかの漢字を当てはめられる。ほんとうはケッヘルを指して、『モーツァルトを“創った”男』と言えればこれほどカッコイイものはない。だが、ケッヘルはけっして創意の人ではないのだ。モーツァルトなりベートーヴェンなりフックス(ウィーンの宮廷楽団で活躍したバロック時代の音楽家で、ケッヘルはこのフックスの研究家としても知られる)なり、あるいは自然なりが創造したものをフォルムとしてまとめ提示することに長けた才能。となればケッヘルはあくまで、『モーツァルトを“造った”男』なのだ」と。
この本の優れた点はいろいろあるが、特にハプスブルグ帝国の絶頂期から消滅までを、ケッヘルの辿った足取りにあわせて、読者に噛み砕いて解説する行は特に素晴らしい。味気の無い歴史教科書などを読むよりは数段面白いし、歴史が頭に入ること請け合いだ。例えば、メッテルニヒ体制の台頭と同時に、私的な教養人のサークルとしてのビーダーマイアー文化やディレッタントと呼ばれる集団が消滅の道を辿ったことが詳細に紹介されている。そして、ウィーンを中心としたハプスブルグ帝国が時代に翻弄され続け、ドイツが歴史の表舞台に姿を現す一方、その姿を消滅させて行く過程が、この本では歴史小説を読むように書き進められる。
モーツァルトは、今でこそクラシック音楽界にあっては別格扱いであるが、モーツァルトの死後しばらくは、忘れ去られた存在と言っては言いすぎであるが、必ずしも評価は高くなかった。そのこともあり、モーツァルトの直筆の楽譜は散逸し、当時作品の全体像を見渡すことは不可能であったのだ。それをケッヘルが逸早く収集し、作品順に番号を振っていった。このことがケッヘルの名を不滅のものにしたのだ。
ケッヘルは、個人的趣味で岩石の収集を行っていた。収集した岩石は、種類別や採取場所などで分類、整理され、現在まで残されているという。要するにケッヘル自身、ケッヘルが生きていた時代の文化潮流であるディレッタントの一人と言ってよかろう。現在で言うと趣味人である。それも玄人はだしの趣味人であったのだ。このことがモーツァルトの全作品に通し番号を付ける時に大いに役立った。
さらに、ケッヘルは、モーツァルトの作品を整理する時に、カードにデータを書き込み、これを基にして通し番号を付けたという。現在、広く使われているカード式整理法を、ケッヘルは当時独自に編み出したのだという。この考えは、突き詰めるとコンピューター処理的発想に行き着く。こうやって見ると、ケッヘルは単にモーツァルトの全作品に番号を初めて振った人という以上に、当時考え得る最善の情報処理を駆使したからこそ、歴史に名を残すことになったケッヘル番号を完成させることができたと言うことができよう。
モーツァルトは、クラシック音楽史上、現在最も多くの人々に愛されている作曲家の一人であるが、ケッヘル番号の謎解きをすることによって、より深くモーツァルトの音楽を理解することができ、愛着も一層深まることにつながる。そのとき、この本「モーツァルトを『造った』男」が、あなの最善の伴侶になることは間違いないことである。なお、巻末に一覧表として「ケッヘルが『確定』した626の楽曲」(K1ピアノのためのメヌエットとトリオト長調~K626レクイエム)が13ページに渡り掲載されているので何かと便利であることを申し添えておこう。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2011年6月15日

書名:指揮者の仕事術
著者:伊東 乾
発行:光文社(光文社新書)
目次:イントロダクション なぜ音を出さない音楽家が生まれたのか?
第1章 「攻撃と守備」から考える(危機管理という仕事)
第2章 聴こえない音を振る(音を出さない演奏家)
第3章 リハーサルこそ真骨頂(プロを納得させるプロ)
第4章 「正しく直す」って何だろう?(魅惑の「ズラシのテクニック」)
第5章 言葉に命を吹き込む仕事(「第九交響曲」の魂を訪ねて)
第6章 片耳だけで聴く音楽?(野生の両耳/知性の利き耳)
第7章 「総合力」のリーダーシップ(指揮者ヴァーグナーから学ぶこと)
終章 夢を見る権利
オーケストラの演奏会では、その中央に必ず指揮者がいる。室内合奏団の場合には、指揮者がいなくても演奏する場合があるが、ほとんどの場合指揮者がいる。その指揮者もフルトヴェングラーやトスカニーニ、ワルターなどの巨匠ともなれば、マエストロと呼ばれ、楽団員はいうに及ばず、一般の聴衆からも尊敬を一身に受けるのである。こんな当たり前の話も、一歩引いて考えればどうも不可思議なことに気が付く。音を出しているのはオーケストラの団員達であり、指揮者ではない。それに、演奏中に指揮者の方を見ている楽団員なんてほんの僅かで、ほとんどの楽団員は楽譜とにらめっこばかりをしていて、指揮者なんて無視している。それに、指揮者の動作は、音が鳴っているからまともに見えるが、もし音を消して見るとするならば、到底、正気の沙汰とは思えない(失礼)ほどなのである。このことは指揮者を正面から見ることが出来る席(例えばでサントリーホールの舞台後ろの聴衆席)で聴くと(見ると)、そう見当外れでないことを理解してもらえると思う。
しからば、指揮者の仕事とはなんなのか?そんな素朴な質問に懇切丁寧に回答してくれるのが伊東乾著「指揮者の仕事術」(光文社新書)なのである。著者の伊東乾氏は、作曲家兼指揮者でベルリン・ラオムムジーク・コレギウム芸術監督。東京大学理学部物理学科を卒業し、第1回出光音楽賞を受賞した経歴があり、著作も多数に上るというわが国クラシック音楽界の重鎮の一人であり、私などは近くにも寄れない存在である。普通、そんな方が本を書くと、やたら難しくて理解不能な内容になりがちなのであるが、この「指揮者の仕事術」は、初心者が読んでも指揮者とはどんな仕事をしているのかが理解することができる内容となっている。イントロダクションからして「なぜ音を出さない音楽家が生まれたのか?―優れた監督が選手の力を千倍にも生かす―」という題が付けられており、ずばり、素人が考える素朴な疑問に答えようとする姿勢がありありと見え、この本なら指揮棒一本で尊敬を一身に集める指揮者という職業の謎を解いてくれそうだ、という期待感を十分に持たせてくれる。
その期待通り、誰もが知っているベートーヴェンの「運命」を例に挙げて指揮者の仕事を解説している。「この作品を演奏する時は、『ジャジャジャジャーン』では表現できない休符が大変重要になります。ベートーヴェンが記した楽譜に忠実に表現するなら、『ジャジャジャジャーン』という音の直前に、『ん』という休符のリズムを補ってやる必要があるのです。これをカタカナで書くと、『んジャジャジャジャーン んジャジャジャジャ―ン』となります。・・・そして指揮者は、この「ん」つまり休符を演奏する唯一のプレーヤーとして、オーケストラのど真ん中に立っているのです。」なるほどなるほど、これでようやく指揮者の仕事の一端が見えて来たぞ、と実感することができるのだ。この辺の様子をインターネットの動画を通して見ることができるのも、この本の特徴の一つである。そして、読者は指揮者の仕事に知らず知らずのうちに引きずり込まれてしまう。それは「西洋音楽には『テンポ』と『リズム』があります。この違いをご存知ですか?」と著者は読者に問いかけてくる。そう改まって訊かれても返答に窮する読者もいるはずだ。そうだ、テンポとリズムは指揮者の大事な仕事の一つであることを、読者は無意識のうちに知らされる。そしてそれは、ピエール・ブーレーズの指揮テクニックの写真解説の話へと繋がっていく。
著者の伊東乾は、音楽を極めるには物理学の知識が必要だということで、東大で物理学を勉強したというから単なる音楽家とは一味違う。指揮をする際の腕や手の「ねじり」や「ひねり」を画像解析技術により解析し、その成果は、ピエール・ブーレーズなどから高く評価されているという。つまり、筆者は、指揮者の仕事を物理学の観点からも解き明かそうとしたわけであり、この経緯についても触れている。この本は全部で7章から構成されているが、特に圧巻なのは第5章言葉に命を吹き込む仕事―「第九交響曲」の魂を訪ねて、と第7章「総合力」のリーダーシップ―指揮者ヴァーグナーから学ぶこと、である。日本人の誰でもが知っているベートーヴェンの第九交響曲。誰でも知っているので、ことさら問題にしようとしない。しかし、「歓喜の歌」が、ベートーヴェンの“苦悩を克服して歓喜に至る”という思想を音楽にした曲と単純に思って疑わない、そのこと自体が危ういのだと筆者は指摘する。「実は、ここに、『第九』が本家本元のヨーロッパで難解とされ、そうひんぱんに演奏されない大きな理由があります。ドイツ語を普通に理解する人々にとって、『第九』は現在でも、矛盾に満ちた不可解な作品、創造的な問いを発し続ける問題作であり続けているのです。」詳しくは本書を読んでもらうしかないが、「歓喜の歌」を文字通り単なる歓喜の歌と捕らえるのは皮相であり、シラーの元の詩とベートーヴェンの作詞部分を正しく理解することこそ指揮者の仕事である、と筆者は言いたいのだ。
第7章「総合力」のリーダーシップ―指揮者ヴァーグナーから学ぶことは、ワーグナーが、ベートーヴェンの「第九」を再評価し、その指揮をした経緯やワーグナーの楽劇とバイロイト祝祭劇場の成り立ちが詳しく紹介されている。特に、舞台裏か見た演奏の方法は、我々が知らない世界だ。オーケストラ・ピットに目隠しが付けられているが、その中でどのようにして指揮者とオーケストラが演奏しているのか、バイロイト祝祭劇場の音響が何故すぐれているかなど、事細かに解説している。俗説ではワーグナーは誇大妄想家とされているが、筆者は、それは間違いだと指摘する。優れた指揮者でもあったワーグナーは、緻密な計算の基に楽劇を作曲し、それらの作品を最上の状態で演奏することができる場として、バイロイト祝祭劇場をつくったのだという。ワーグナーが優れた指揮者であったことが文献に残されている。
この本のあとがきで筆者は「音を出さない音楽家である指揮者の究極の仕事術は、音楽を通じて生きる夢や希望を、みんなと分かちあうことです」としている。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2011年2月06日

書名:オーケストラの経営学
著者:大木裕子
発行:東洋経済新報社
目次:第1楽章 「のだめ効果」はあったのか 業界の特徴と規模
第2楽章 「音大生」の投資対効果 オーケストラの人々
第3楽章 なぜ赤字なのに存続するのか オーケストラの会計学
第4楽章 オーケストラの経営戦略 外部マネジメント
第5楽章 指揮者のリーダーシップ 小澤征爾かカラヤンか
第6楽章 世界的音楽家はいるのに日本に世界的オケがないわけ
自治体の財政難に伴って、全国で芸術活動への補助金の打ち切りが相次でいる。また、不況を口実に企業が芸術活動を支援する予算の削減を行う傾向も続きそうだ。そうなると、クラシック音楽、その中でもオーケストラを運営することがかなり難しい局面を迎えつつあることは、避けて通れない現実だ。そうなると「自治体はオーケストラに支援を!」「企業もオーケストラに支援を!」というスローガンを、至極当然なことと捉えがちだ。だがまてよ、そもそもこの小さな国土に、こんなにも多くのオーケストラがあること自体が問題なのではないか?と私などは勘ぐってしまう。今、大都市には歯科医院が乱立し、都心ではほんの10メートルも歩くと歯科医院の看板に出くわす。この原因はというと、大学が歯学部の卒業生を大量に排出した結果で、需要があったからではないそうである。つまり、供給過多が原因であり、この結果、歯科医院の経営自体も難しくなっている。
同じことがオーケストラ経営にも言えるのではないか、などという素朴な疑問に答えてくれるのが、この大木裕子著「オーケストラの経営学」なのである。著者の大木氏は、東京芸術大学を卒業し、ヴィオラ奏者として東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団に入団し、実際の演奏活動の経験がある。その後、一転して経営学の道を目指し、現在、京都産業大学経営学部准教授の肩書きを持つ。つまり、評論家の立場でなく、オーケストラ活動の経験を通して、現在はオーケストラの経営の研究者という、あまり他に例がない立場だ。言ってみれば、サッカーや野球の選手が引退し、サッカー解説者や野球解説者になるのとよく似ており、信頼性は高いものがある。まず、この本で日本にはいったいいくつのオーケストラが存在しているのかを探してみると、「アマチュアオーケストラ(約700)のほかに、日本には日本オーケストラ連盟に所属する23のプロフェッショナル・オーケストラがあり、これに準会員や音楽家ユニオンに所属する団体を加えると、28のプロフェッショナル・オーケストラがあって、約2000人の演奏家を雇用している」そうである。
東京には、首都圏を合わせると10のオーケストラがあり、これほどたくさんのオーケストラがある都市は他にないといっていいと、同書は指摘する。東洋の小さな島国の首都が、世界でもまれな数のオーケストラを擁している。この点を軸に考えないとオーケストラの経営問題の解決の糸口は見つからない。日本はまだまだ西洋音楽を勉強しなければならないのであるから、決して多くはないとみるか、ヨーロッパの都市以上にオーケストラがあるのは供給過剰、とみるかによって大きな食い違いが生じる。量の問題は別にして、質の問題はどうであろうか?「筆者の経験上、日本のアマチュア・オーケストラのレベルは世界一、といって過言ではないのだ」と大木氏はいう。これでほっとした。しかし、数だけ多くて質の方はさっぱりであったら、やっぱり過剰供給だと一刀両断に切り捨てられるのではあるが、質は世界一といわれると、そうもいえないことになるから、話はややっこしくなる。
貧乏人である私は、いつもクラシック音楽家のお金の問題について考えてしまう。コンサートで配られる演奏家の経歴をみるとほとんどが4年制大学を卒業し(それも東京芸術大学卒か桐朋学園卒が大半を占めている。これはわが国のクラシック音楽界が稀にみる学閥体制の結果のためなのか、はてまたこれが実力なのであろうか)、海外の音楽学校へ留学し、帰国してからようやくリサイタルを開くケースが多い。リサイタルが好評で元がとれればいいが、聴衆を集められなければ持ち出しで終わりだ。この本には、①3歳からヴァイオリンを始めて、普通高校から大学受験するケース=996万円②大学の納付金=812万円③楽器の費用=1150万円、締めて2958万円という数字が載っている。これに海外留学費が加算される。そして、次の中見出しを見たら「お金を気にしたらわりにあわない」とあった。これで納得。
また、この本には「なぜ日本には世界的なオーケストラがないのか」という、一瞬ギクッとするような中見出しもある。「日本のアマチュア・オーケストラのレベルは世界一」と断言した筆者はことプロのオーケストラとなると手厳しい。「もともと日本には、教会の響きの中で賛美歌を歌いながらハーモニー(調和・和声)を創っていく習慣がない。そのため、お互いの音を響き合ってハーモニーを創っていく意識がどうしても低くなっているようにみえる」「日本のオーケストラは『職人的だが、創造性高くない』といえるだろう」。御説ご尤もではあるが、私はもう少し日本のオーケストラ弁護したい。多くの団員が教会の響きの中で育っていないのだから、しょうがない。それにしては、実際にコンサートで熱演するオーケストラの演奏を耳よくにする。日本のオーケストラは、ハンディを何とか克服しようと努力していると思う。それにしてもこの本は、オーケストラを、その舞台裏から見た鋭い視点が随所にちりばめられており、日本のオーケストラを語る上で欠かせない本となっている。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2010年11月23日

書名:ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール~市民が育む芸術イヴェント~
著者:吉原真里
発行:アルテスパブリッシング
目次: 序章 ドラマの幕は開く
第1章 第13回クライバーン・コンクールの幕開け
第2章 クライバーン・コンクールとは
第3章 予選
第4章 クライバーン・コンクールを支えるコミュニティと人びと
第5章 準本選
第6章 クライバーン・コンクールの舞台裏
第7章 本選
終わりに クライバーン・コンクールのもつ意味
「ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール」の名は、クラシック音楽ファンには馴染み深いコンクールではあっても、多くの日本人にとっては、「それって何?」ということになろう。少なくとも、2009年の第13回目の「ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール」が行われて、ここで辻井伸行が優勝するまでは・・・。
辻井の優勝がテレビを通じて報道されるや否や、もうずっと前からこのコンクールを多くの日本人が知ってたかのように国民的話題を集め、辻井は一躍国民的スターの座に付いたのだ。普通なら、熱しやすく冷めやすい国民性が身上の日本人なら、ここで終わりのはずであるのだが、辻井の場合はどうも少々違う。何の衒いもない辻井の人柄なのか、未だに多くの日本人が辻井の存在が気になってしょうがないようなのだ。そして、多分プロの音楽家が聴いても辻井の演奏は十分満足できる内容を備えているといっても間違いなかろう。スター性と実力を兼ね備えた辻井のような存在は、例外的存在なのだ。
ところで私自身「ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール」が、冷戦当時、チャイコフスキー国際コンクールで、米国人のヴァン・クライバーンが優勝し、国民的英雄となり、それを記念して始められたピアノコンクールということぐらいしか知らないことに、今頃になって気が付いた。当時「レコード芸術」誌にヴァン・クライバーンのレコードの広告が大きく載り、若々しいクライバーンの姿が目に浮かぶ。その後、クライバーンは精神障害から人とは会わない生活をおくっているようだ、といった報道があり、クライバーンも過去の人かと思っていたら、今回、歳はとったが元気そうな姿を見て、懐かしい気分にさせられた。そんな「ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール」を詳細に紹介したのが吉原真理著「ヴァン・クライバーン国際ピアノ・コンクール~市民が育む芸術イヴェント~」(アルテスパブリッシング刊)なのである。
この本の優れたところは、クラシック音楽そのものを紹介するというよりは、コンクールを通じて垣間見えるアメリカという国の国民性を詳細にレポートしていることであろう。ピアニストは単にアメリカに来て、コンクールで演奏して帰る、なんてほんの表面的なことであり、実はその裏には、街を挙げての歓迎準備、特にホームステイ先の家庭の気配りには敬服してしまう。「アメリカの金持ちだからできる芸当さ」と言ってしまえばそれまでだが、逆に金持ちならできるのかと問われれば、ノーであろう。やはり、音楽への愛情、それに海外から来るピアニストへのおもてなしの精神、いずれもこの本にその辺のことがこと細かく紹介され、コンサートの舞台裏は大変なもんだ、と感心させられる。
逆に、これらの精神は、昔の日本人が大切にしてきたことであることに気付かされる。今の日本人は、あたかもどこそこのコンクールで何位に入賞したかにしか関心がないようだ。これでは、受け入れる側からすれば、「日本人はどたどたと集団でコンクールに来て、結果ばかり気にして帰ってしまう、なんて不思議な国民」と考えるかもしれない。欧米人にとって音楽コンクールとは、人と人の繋がりの場であることをこの本は示している。日本人といおうか、東洋人はもっとその辺を考えないと、将来双方のズレが生じかねないかもしれないことを、この本は暗に示しているように、私には思えてならない。
この本の特徴の一つは、コンサートの表面的な運営法をだけ追うのでなく、コンサートのコンセプトが如何に大切かを教えてくれることである。「1987年の第8回コンクールから20年にわたって、ロジンシキーは、コンクールの運営委員長そしてコンクールの母体組織であるクライバーン財団の会長として、見事なリーダーシップを発揮し、クライバーン・コンクールを、ショパン・コンクールやリーズ・コンクールなどど並んで、世界でもっとも権威あるピアノ・コンクールへと発展させた」とある。このロジンスキーにハワイ在住の著者・吉原が直接インタビューしている(なお、ロジンスキーが2011年のチャイコフスキー・コンクールの組織委員会最高顧問兼運営委員会委員長に就任することをこの本の最後で吉原は紹介している)。
同コンクールにアマチュア・コンクールがあることをこの本で私は初めて知った。また、今回辻井と優勝を分け合った中国のハオチェン・チャンなど、出場者への直接インタビュー記事も貴重なものだ。最後に、同コンクールに関わっている指揮者のコンロンのスピーチに私は強く惹かれた。「芸術において、一番などというものはない。仲間と競争をしようなどと思うものは、才能のとんでもない浪費である。本当の競争は、自分の持っている精神的、知的、情感的な要素を引き出すための、自分自身との闘いであるべきだ。真の競争はひとつしかない。それは、自分の持っている可能性を、生きているうちに存分に引き出すための、時間との競争なのだ」。この言葉の中にクライバーン・コンクールの魂を見る思いがした。(蔵 志津久)
コメント/トラックバック投稿 »
2010年11月12日

書名:秘密諜報員ベートーヴェン
著者:古山和男
発行:新潮社(新潮新書)
目次:第1章 〈不滅の恋人〉への手紙とは
第2章 ナポレオンの大陸制度
第3章 ベートーヴェンとブレンターノ家の人々
第4章 1812年7月、テプリッツ
第5章 「手紙」の再検証
第6章 大崩壊
第7章 〈不滅の恋人〉の去ったヨーロッパ
第8章 結論
ベートーヴェンの名を聞けば、謹厳実直に音楽一筋の芸術家で、それ以外の世事には疎かったといのが、我々の大体の共通認識ではなかろうか。以前読んだ本には、ベートーヴェンは数字に弱く、コーヒー豆を使って足し算とか、引き算を行っていたなどと書かれていた。要するにベートーヴェンから音楽をとったら何も残らない、といった極端な見方が圧倒的に多かったわけである。
ただ一つだけ、ナポレオンが独裁者になったときに「ナポレオンも俗物だ」と言い、交響曲第3番「英雄」の表紙を破り捨て、楽譜を床に叩きつけたという逸話が残っており、現在まで実際にあった話として信じられている。つまり、ベートーヴェンも政治に影響を受けて作曲活動を続けていたことをうかがわせる。ただ、この話も特別ベートーヴェンが実際の政治に関心が強かったということでなく、戦争より平和を願う作曲家であった、ということを裏付ける程度の軽い話としか捉えられてはいない。
ところが、古山和男著「秘密諜報員ベートーヴェン」(新潮新書)によると、これらのこと全てが、全くのつくり話であるというのである。ベートーヴェンは、当時のウィーンを中心に、積極的に政治活動に身に委ね、秘密諜報員(つまりスパイ)として大活躍していたというのだ。誠にもって大胆不敵な推理であり、これまでの音楽以外の世事に疎いというベートーヴェンのイメージが、根底から音を立てて崩れ去ってしまう。
それでは古山氏は、何を根拠にこんな大胆不敵な推理をするのか。その答えは、べートーヴェン自ら書いた3通の有名な「不滅の恋人への手紙」の内容にあるという。現在に至るまでこれらの手紙は「恋文」として知られ、相手は誰なのかが謎になっている。古山氏によると「この『手紙』が、恋文を装った『密書』、思想的で政治的なメッセージを含む、一種の『暗号通信文』」だというのだ。詳しくは本書を読んでもらう他ないが、古山氏は、ナポレオンの大陸封鎖政策とロシア遠征との関わりで、ベートーヴェンが書いた「不滅の恋人への手紙」を解釈すべきだと主張する。
では、直接ベートーヴェンが諜報活動した証拠はあるのか。実はあるのである。例えば「1809年、オーストリア軍が降伏したウィーンの町を、楽譜やメモ帳を持って歩いていたベートーヴェンが、スパイ容疑で尋問されたとい話が残っている」のだそうだ。また、諜報活動を行うのに欠かせない資金であるが、「ベートーヴェンはプラハで得た金60ドゥカーテンを持っていた。秘密諜報員として行動するのにこれ以上有利な条件を備えたものはいなかった」と見る。では何故、為替や小切手でなく金なのかというと「諜報活動を成功させるには、どこでも通用する現金を潤沢に用意するのが鉄則」だと古山氏は主張する。
そして、ベートーヴェン自身が英雄交響曲の楽譜の表紙を破り捨てて(あるいはペンで消して)、楽譜を床に叩きつけたという説に対し、古山氏は「表紙を『破ってもいない』し、(ナポレオンへの)献呈辞を『ペンで消してもいない』はずだ」と俗説を一蹴する。つまり、これまで信じられてきた逸話には、確たる証拠が残されているわけではないのである。
古山和男著「秘密諜報員ベートーヴェン」は、ヨーロッパの歴史を克明に紐解きながら、一つ一つ検証を試みるという、気の遠くなるような作業を通して、ベートーヴェンの真の姿を炙り出そうとした労作である。本のタイトルだけを見ると、何か如何わしい雰囲気があるが、中身は全く異なり、新しいベートーヴェン像の創出に真正面から取り組んだ、意欲的な快著といえる。古山氏は、まだまだ新事実のデータを有しているそうなので、第2弾、第3弾の出版が待たれる。(蔵 志津久)(2010/8/23)
コメント/トラックバック投稿 »
2010年11月12日

書名:バイオリニストに花束を
著者:鶴我裕子
発行:中央公論新社
目次:演奏家見ならい記
(もぐりで聴いたカラヤンのとてつもない「何か」 ほか)
N響という“カイシャ”
(花粉アラモード ほか)
外国ツアー・アラモード
(もはや「異国」ではないヨーロッパ ほか)
オーケストラのゲストたち
(チョン・キョンファとヒラリー・ハーン ほか)
定年までのカウントダウン
(「めしばん」は原点 ほか)
この本はNHK交響楽団(この本では「N狂」または「わが社」の“愛称”でたびたび登場)の第一ヴァイオリニストとして活躍してきた鶴我裕子さんが、これまで書き連ねてきたエッセイを1冊の単行本にまとめ新たに発刊したものだ。236ページにわたり、鶴我さんの生い立ちから、愛し続けた「N狂」を“定年退職”するまでの歴史が書きとめられている。読む前はエッセイ集ということで気軽に読み始めたのであるが、読み終わった後は、何かずしっとした重みを感じた。これはきっと会社を定年退職した人にしか分らない人生の重みなのだろう。
と書くと何か難しい本のように思うかもしれないが、「演奏家見ならい記」「N響という“カイシャ”」「外国ツアー・アラモード」「オーケストラのゲストたち」「定年までのカウントダウン」の各中見出しごとにまとめられたエッセイの数々は、抱腹絶倒の分を含めて、どのエッセイも鶴我さんの鋭くも優しい目線が行き届き、思わずニヤリとしてしまうのだ。
例えば「オーケストラのゲストたち」編では、世界一流の演奏家でも鶴我さんの筆にかかればケチョンケチョンだ。「チョン・キョンファは、激変した。良いほうに。同じ人かと目を疑うほどだ」と軽くジャブを飛ばす。ということはその前は・・・これは読んでのお楽しみ。女性が女性を見る目は恐ろしいのだ。鶴我さんは男に対しても鋭い。「若きクレーメルが、初めてN響に来た時を思い出す。何とも言えない容貌だった。チャイコフスキーの協奏曲を弾き始めると、下あごをカパッとあけて、いっそう変な顔になった」のだそうだ。最後は「楽団員はしびれていた」と評価を下すが、クレーメルとしては東洋の島国まで来て、自分がそんな風に見られていたなんてゆめゆめ感じていなかっただろうに。なんだか可哀そう。
この本は、普通の人では知りえないオーケストラの楽屋裏も垣間見せてくれる。「知られざる難行?コンマスの左隣り?」では、「アシスタント・コンサートマスター」の“地獄”の存在が紹介されている。コンサートマスターは誰でも知っているが、このコンマスを影で支えているのがアシスタント・コンサートマスターなのである。何故地獄の存在なのかは本書を読んでいただきたいが、要するに偉いコンサートマスターにいかに合わせて、オケ全体を引っ張っていかなくてはならないかという中間管理職の存在そのものが地獄なのだ。普通の会社に例えるなら、指揮者が社長とすると、専務がコンサートマスター、そしてこのワンマン専務に仕える部長か課長がアシスタント・コンサートマスターなのであろう。しかも、この地獄の役割は日本のオケ独特のものというから、ますます“N狂”が日本の“会社”そのものに見えてくる。
本書は、一般のリスナーがクラシック音楽を聴くときに大いに参考になるはずだが、私は、将来オーケストラに“入社”して“社員”になりたいと考えている若い人たちに読んでもらいたいものだ思う。この本の行間からは、演奏家としてオケのメンバーとして一緒にやっていく厳しさと同時に、楽しさも伝わってくる。最後に鶴我さんが“会社”を“定年退職”する時の話などは、思わずホロリとさせられた。(蔵 志津久)(10/7/12)
コメント/トラックバック投稿 »