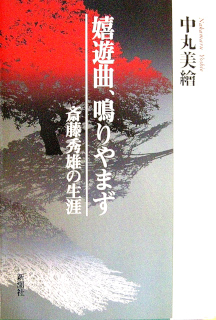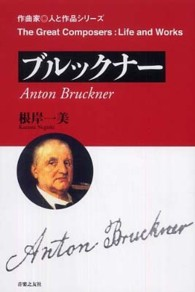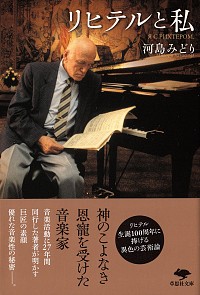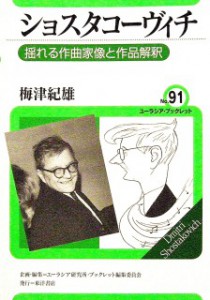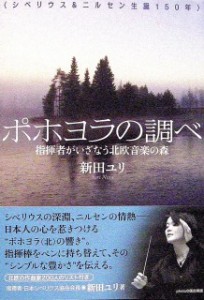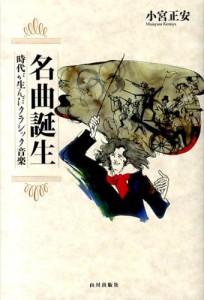2017年4月05日
◇「嬉遊曲、鳴りやまず 斎藤秀雄の生涯」(中丸美繪著/新潮社)
書名:嬉遊曲、鳴りやまず 斎藤秀雄の生涯
著者:中丸美繪
発行:新潮社(1996年7月書籍、2002年8月文庫本が発刊されたが現在は絶版。
ただし、ネット通販サイトから購入可能)
目次:第1章 斎藤秀雄の育った家
第2章 演奏家になる夢と希望
第3章 戦火のなかで
第4章 「子供のための音楽教室」
第5章 嬉遊曲、鳴りやまず
この書籍「嬉遊曲、鳴りやまず 斎藤秀雄の生涯」(中丸美繪著/新潮社)は、現在「サイトウ・キネン・オーケストラ」にその名を残す、チェリストであり指揮者であり教育者でもあった斎藤秀雄(1902年―1974年)の生涯を描いた、筆者渾身の評伝である(日本エッセイスト・クラブ賞、ミュージック・ペンクラブ賞受賞)。小澤征爾は1992年に恩師である斎藤秀雄の名を冠して「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」を創立したが、2015年から「セイジ・オザワ 松本フェスティバル(OMF)」として新たなスタートを切っている。このとき、「サイト・ウキネン・オーケストラ」の名称も変更するかどうかを楽団員に訊いたところ、今後も「サイト・ウキネン・オーケストラ」の名称で行こうという結論に達したという。
海外で演奏する場合や国内でも世代交代が進み斎藤秀雄の名前を知らない若い演奏家が増えつつあることから、名称の変更を考えたのだろうと思う。しかし、楽団員たちは「サイト・ウキネン・オーケストラ」を使い続けることを選択したのだ。それだけ斎藤秀雄に対する敬愛の気持ちが今でも根強いということなんだろうと思う。この書籍の特徴の一つは、単なる斎藤秀雄の評伝に止まらず、わが国のクラシック音楽界の創成期の様子が手に取るように明らかにされていることだ。これらを読むと斎藤秀雄の周りには、わが国のクラシック音楽界で重要な役割を果たす人物が何人も登場することが分かる。斎藤秀雄自身は、アマチュアのマンドリンクラブの指揮者として頭角を現し、チェリストとしてドイツに渡り、帰国後は子供のための音楽教室の教育者として、その生涯を捧げることになる。
この書の冒頭は、著名な英語教育者であった斎藤秀雄の父親の斉藤秀三郎に関する記述で始まる。直接音楽とは関係ないが、この部分もなかなか興味深い。斉藤秀三郎は18歳で仙台で英語塾を開き、後に仙台英語学校を創設する。詩人の土井晩翠はその一回生であったという。その後、28歳で第一高等学校に教授として就任する。その3年後、31歳の時、神田錦町に正則英語学校(現・正則学園高等学校)を創立して自ら校長となった。斉藤秀三郎は生涯に200冊の英語に関する書籍を残している。昔、私の家にも斉藤秀三郎の英語の辞書が置いてあり、斉藤秀三郎という名前を私は早くから知っていた。
しかし、それが音楽家の斎藤秀雄の父親であると知ったのは、大分後になってからだ。斉藤秀三郎が妻とらと新居を構えたのは、東京の築地明石町であった。この築地明石町という場所そのものが斎藤秀雄の人格形成に大きく影響を及ぼしたことは疑いないことだ。というのも、築地明石町は、明治政府が初めて東京に外国人居留地を開いた場所であったからだ。「教会から鐘の音が鳴り響き、ミッション・スクールからはオルゴールの音が漏れていた。パン屋や牛乳屋の配達までが讃美歌を口ずさむといわれていた。
日本語よりどこか英語の似合う町だった。こういったエキゾチシズム漂う明石町16番地に、秀雄は生まれ、幼い日々を過ごしていた。とらは熱心なクリスチャンであり、秀雄は姉たちとともに日曜学校に連れて行かれた。オルガンの音に合わせて讃美歌を歌った」。明治40年前後にこういった環境下で過ごした日本人はそう多くはなかったろう。それでは、斎藤秀雄はすんなりと音楽の道を目指したかというと、そうではなかったのだから面白い。
実は、斉藤秀雄が最初に目指したのは、造船家への道であった。当時は男が音楽家を目指すと言ったら周囲が引き留めるような雰囲気があり、将来の生活の安定を考えるなら技術屋になるなるのが最善の道であることは誰の目にも確かなことだ。ところが父母の故郷にある第二高等学校を受験したが、斉藤秀雄は受験に失敗してしまう。ここで造船家への夢は潰えたのだ。もし、受験に合格していたなら音楽家としての斉藤秀雄は存在しなかったことを考えると、わが国のクラシック音楽界にとっては非常にラッキーな失敗だったと言わざるを得ない。ここで注目すべきことは、斉藤秀雄はもともと理科系的な発想の人物であったことである。
このことが後に、世界初と言われる指揮に関する書籍「指揮法教程」(1956年刊)に結実、いわゆる“斉藤メソッド”を生むことになるのである。東京大学理学部在学中に作曲の道を歩み始めた別宮貞雄は次のように語っている。「普通日本の音楽家は、外国で勉強したことを伝えるというのが多いが、斉藤先生の場合は違うんでね。自分で分析して教えるという科学者的やり方をしたんだ。・・・西洋近代科学がそうであったように、西洋近代音楽の精髄を、科学的研究によって分析して演奏解釈として生徒に教えたんですよ。斉藤先生はけっして音楽の神秘を無視したではないが、90パーセントは自然科学のように音楽をやっていたんですよ」。理科系出身の作曲家である別宮貞雄の言葉だけに、斉藤秀雄が音楽教育で何をどのようにして成し遂げたのかを鋭く見抜いていたということができよう。
斉藤秀雄の後半生の大きなテーマとなったのは、何といっても「子供のための音楽教室」の創設とその教育である。1950年、斉藤秀雄48歳の時であった。「子供のための音楽教室」を始めるに当たり、斉藤たちは、「私たちの立場」という文書をつくっている。この冒頭で「今までの私どもの国の音楽教育には、ふたつの大きな欠点がありました。(1)教育を受けはじめるのがおそすぎる。(2)音楽の知識を習うことが軽視されるか、さもなければ抽象的にだけおこなわれた」と指摘している。そしてこの文章の最後には、「子供のための音楽教室」の5つの課題が掲げられているが、特に注目されるのが5番目の課題「個人の演奏だけでなく、合唱、合奏の訓練をする」であろう。斉藤の考えには、最初からオーケストラの結成という大テーマがあったのである。
オーケストラが存在すれば、そこには当然指揮者の育成もなければならない。そのために斉藤自ら「指揮法教程」を執筆し、これを教材として、斉藤メソッドによる指揮者教育が行われた。その斉藤メソッドをいち早く世界へ向かって体現したのが、桐朋学園音楽科の一期生の小澤征爾、さらに秋山和慶たちだったのである。この書には、北軽井沢の夏合宿で、ござに座って子供たちの演奏の指揮をする若き日の小澤征爾の珍しい写真が掲載されている。
斉藤秀雄の厳しい教育現場の模様がしばしば登場する。眼鏡を床にたたきつけるほど怒りだしたら誰も止めることはできなかったほど。でもそれがあったからこそ、渡米した斉藤の桐朋学園オーケストラは、ニューヨーク・ポスト紙から絶賛を受けるほどまで成長できたと言えよう。そして、斉藤秀雄は「肉体こそ失ったが、いまだに弟子達の内部を彷徨している」のである。
この書は、1996年7月に単行本で、2002年8月に文庫本で、それぞれ新潮社から発刊されたが、今回、新潮社に問い合わせたところ絶版になっているとの回答。しかし、ウェブ通販サイトからは購入は可能だ。これは、斉藤秀雄の評伝という意義ある書籍であると同時に、わが国のクラシック音楽界の基盤が如何に形づくられて行ったかの生き証人のような書籍。絶版とはあまりに残念なことではある。(蔵 志津久)