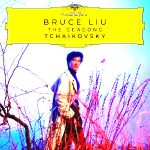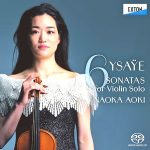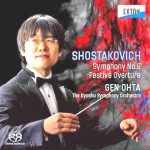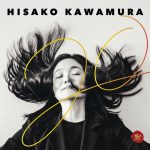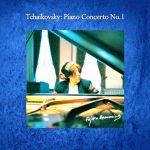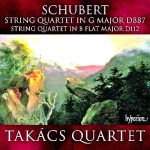2024年9月12日
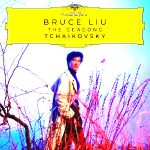
チャイコフスキー:「四季」
ロマンス ヘ短調 作品5
ピアノ:ブルース・リウ
CD:ユニバーサルミュージック UCCG-45102
2021年10月、第18回「ショパン国際ピアノ・コンクール」で優勝し、世界の舞台へと躍り出たブルース・リウが、チャイコフスキーのピアノ独奏曲の中で最もよく知られた「四季」を収録。「四季」は、サンクトペテルブルクの音楽雑誌「ヌーヴェリスト」が、毎月その時期の風物を描いたピアノ小品をチャイコフスキーに委嘱し、1876年を通して毎月1曲ずつ掲載された作品。チャイコフスキー:ロマンス ヘ短調 作品5も収録。
ピアノのブルース・リウは、1997年パリで生まれる(カナダ国籍)。両親は中国・北京からのフランス留学生で、後にカナダへ移住。モントリオール音楽院で学び、ヴェトナム出身のダン・タイ・ソン(1980年アジア人初の「ショパン国際ピアノコンクール」優勝者、現在カナダ、モントリオール在住)に師事。「仙台」、「モントリオール」、「テルアヴィヴ」、「ヴィセウ」などの国際ピアノ・コンクールで入賞、そして2021年第18回「ショパン国際ピアノ・コンクール」で優勝を果たす。クリーヴランド管弦楽団、イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団、モントリオール交響楽団などのオーケストラと共演し、中国NCPA管弦楽団とは北米ツアーを行う。近年では、ウクライナ国立交響楽団およびリヴィウ・フィルハーモニー管弦楽団との2年連続の中国ツアーや、サル・ガヴォーでのラムルー管弦楽団との共演がある。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年9月09日

<CD1>
ショパン:24の前奏曲 Op.28
<CD2>
スクリャービン:24の前奏曲 Op.11
矢代秋雄:24の前奏曲
ピアノ:藤田真央
CD:ソニーミュージック SICC-30894 (2CD Blu-spec CD2)
ピアノの藤田真央(1998年生れ)は、東京都出身。小学生の時、「全日本学生音楽コンクール」小学生の部で優勝。この時、審査員を務めた野島稔(1945年―2022年)に後に師事することになる。その後、東京音楽大学で学ぶ。2013年第5回「ロザリオ・マルチアーノ国際ピアノコンクール」日本人初の第1位、併せてワーグナー・ヴェルディ賞を受賞。2015年第1回「若い音楽家のための珠海国際モーツァルトコンクール」ピアノ部門グループBで第1位。2016年第20回「浜松国際ピアノアカデミーコンクール」第1位。2017年第27回「クララ・ハスキル国際ピアノコンクール」第1位、併せて聴衆賞などの3つの特別賞受賞。これは日本人では河村尚子以来、3人目の優勝。2019年第16回「チャイコフスキー国際コンクール」ピアノ部門第2位。2020年第21回「ホテルオークラ音楽賞」、第30回「出光音楽賞」受賞。2021年スイスのヴェルビエ音楽祭に招かれ、モーツァルトのピアノ・ソナタ全曲を演奏し絶賛を博す。2022年、拠点をベルリンに移す。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年9月05日
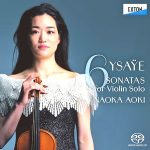
イザイ:無伴奏ヴァイオリンソナタ 作品27
第1番 ト短調
第2番 イ短調
第3番 ニ短調「バラード」
第4番 ホ短調
第5番 ト長調
第6番 ホ長調
ヴァイオリン:青木尚佳
CD:EXTON OVCL-00840
いま最も注目されているヴァイオリニストの一人である青木尚佳は、2022年にミュンヘン・フィルのコンマスに就任し、さらなる飛躍を続けている。このCDは、紀尾井ホールでのイザイ無伴奏ソナタ全曲演奏会の前日に行われたセッション録音。
ヴァイオリンの青木尚佳(1992年生まれ)は、東京都出身。11歳より堀正文氏に師事した後、2009年、桐朋学園大学音楽学部ソリスト・ディプロマコースに最年少で合格し、2011年に修了。同年9月より英国王立音楽大学に留学し、2015年7月に卒業。卒業に際し、全卒業生の中から男女各1名ずつ贈られる「タゴール・ゴールドメダル」を英チャールズ皇太子より授与される。2014年「ロン=ティボー=クレスパン国際コンクール」第2位、併せてコンチェルトの最良の解釈に贈られるモナコ大公アルベール二世賞を受賞。また同年10月、中国・チンタオで行われた第4回「中国国際ヴァイオリンコンクール」第2位。2015年7月に受賞記念リサイタルを東京の浜離宮朝日ホールで開催。その後、フランス各地でリサイタルを開催。2004年第5回「若い音楽家の為のチャイコフスキー国際音楽コンクール」にて最年少ディプロマを受賞。2009年第78回「日本音楽コンクール」第1位、併せてレウカディア賞、鷲見賞、黒柳賞を受賞。2016年第6回「仙台国際音楽コンクール」第3位。現在、ABRSM(英国王立音楽検定)より全額奨学金を得て英国王立音楽院に在学。2022年3月ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団初となる女性のコンサートマスターに就任。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年9月02日
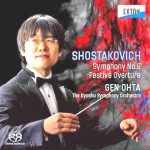
ショスタコーヴィチ:交響曲第5番
祝典序曲
指揮:太田 弦
管弦楽:九州交響楽団
録音:2024年4月11~12日、アクロス福岡シンフォニーホール(ライヴ収録)
CD:オクタヴィアレコード OVCL-00853
このCDは、2024年4月、九州交響楽団首席指揮者に就任した太田 弦の就任披露演奏会のライヴ録音盤。
指揮の太田 弦(1994年生れ)は、北海道札幌市出身。東京芸術大学音楽学部指揮科を首席で卒業。学内にて安宅賞、同声会賞、若杉弘メモリアル基金賞を受賞。現在同大学院音楽研究科指揮専攻修士課程に在籍。2015年第17回「東京国際音楽コンクール〈指揮〉」で第2位ならびに聴衆賞を受賞。2022年「渡邉暁雄音楽基金音楽賞」受賞。2019年4月より2022年3月まで大阪交響楽団正指揮者。2023年4月より仙台フィルハーモニー管弦楽団指揮者、2024年4月より九州交響楽団首席指揮者に就任。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年8月29日
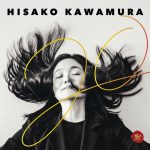
<プロローグ>
1. シューマン:献呈 作品25の1(歌曲集「ミルテの花」作品25 第1曲)[クララ・シューマン編]
<20 – Twenty>
2. R.シュトラウス:さびしい泉のほとり 作品9の2(4つの情緒ある風景 作品9 第2曲)
3. シューベルト:楽興の時 第3番 ヘ短調 D 780 / 作品94の3
4. バルトーク:スケルツォ Sz. 71 / BB. 79の5(15のハンガリーの農民の歌 Sz. 71 / BB. 79 第5曲)
5. ベートーヴェン:エリーゼのために WoO 59
6. R.=コルサコフ:熊蜂は飛ぶ(歌劇「皇帝サルタンの物語」第3幕第2場 間奏曲)[ラフマニノフ編]
7. スカルラッティ:ソナタ ロ短調 K. 27
8. プロコフィエフ:前奏曲 ハ長調「ハープ」 作品12の7(10の小品 作品12 第7曲)
9. ブーランジェ:新たな人生に向かって
10. 矢代秋雄:夢の舟[岡田博美編]
11. ブラームス:間奏曲 ハ長調 作品119の3(4つの小品 作品119 第3曲)
12. リスト:愛の夢 S. 541の3(3つのノットゥルノ S. 541 第3曲)
13. ショパン:即興曲 第3番 変ト長調 作品51
14. ラフマニノフ:エレジー(幻想的小曲集 作品4 第1曲)
15. バッハ:羊は安らかに草を食み(カンタータ第208番「楽しき狩こそわが悦び」 第9曲)[エゴン・ペトリ編]
16. プーランク:バッハの名による即興的ワルツ ホ短調 FP.62
17. フォーレ:即興 作品84の5(8つの小品 作品84 第5曲)
18. メシアン:夢の触れられない音…(8つの前奏曲集 第5曲)
19. 武満徹:雨の樹素描 II-オリヴィエ・メシアンの追憶に-
20. コネッソン:F. K. ダンス(イニシャルズ・ダンシズ 第3曲)
21. ドビュッシー:夢想
<エピローグ>
22. 坂本龍一:20220302サラバンド
ピアノ:河村尚子
CD:ソニーミュージック SICC 19080
日本を代表するピアニスト、河村尚子。2004年11月、日本デビューを飾って以来20年という節目となる今年、パーソナルな小品を集めたアルバムをリリース。アルバムタイトルは「20 -Twenty-」(トゥエンティ)。これまでの20年にわたる演奏活動の中で、河村が大きな影響を受け、大切なものとして愛蔵し、また折に触れて愛奏してきた宝物のようなミニアチュールともいうべき作品たちを盛り込んでいる。
ピアノの河村尚子は、兵庫県西宮市出身。5歳で渡独。ハノーファー音楽演劇大学で学ぶ。同大学在学中の2006年「ミュンヘン国際コンクール」第2位、2007年「クララ・ハスキル国際コンクール」で優勝し一躍世界の脚光を浴びる。2009年度「出光音楽賞」、「新日鉄音楽賞フレッシュアーティスト賞」、「日本ショパン協会賞」、2012年「芸術選奨新賞」、2013年「ホテルオークラ音楽賞」、2019年第32回「ミュージック・ペンクラブ音楽賞」クラシック部門独奏・独唱部門賞、2019年第12回「CDショップ大賞2020」クラシック賞 、2019年第51回「サントリー音楽賞」受賞。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年8月26日
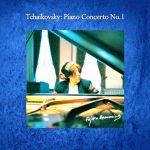
チャイコフスキー:ピアノ協奏曲 第1番
リスト:ラ・カンパネラ(パガニーニによる大練習曲 S.141の3)
「奇跡のカンパネラ」より
「永久への響き」より
「哀愁のノクターン」より
「カーネギー・ホール・ライヴ」より
「フジ子・ヘミングの奇蹟」より
ピアノ:フジコ・ヘミング
指揮:オリヴァー・フォン・ドホナーニ
管弦楽:チェコ・ナショナル交響楽団
録音:チャイコフスキー:ピアノ協奏曲 第1番
チェコ・ナショナル交響楽団が2001年10月~12月にかけて来日ツアーを行なった際、
ソリストに起用されたフジ子の協奏曲演奏を3公演ライヴ録音(12月4日、6日&20日)
したもので、今回初登場となる未発表音源。
5つのラ・カンパネラ
①「奇蹟のカンパネラ」より(録音:1999年6月11日、ビクタースタジオ)
②「永久への響き」より(録音:1999年秋、東京オペラシティ・ライヴ)
③「憂愁のノクターン」より(録音:2000年3月25日、ビクタースタジオ)
④「カーネギー・ホール・ライヴ 2001」より
(録音:2001年6月7日、カーネギー・ホール・ライヴ)
⑤「フジ子・ヘミングの奇蹟」より
(南西ドイツ放送音源 ドイツSWR放送局(旧SDR2)録音:1988年6月)
CD:ビクターエンターテインメント VICC-77001
このCDは、2001年にチェコ・ナショナル交響楽団との共演のライヴ録音で、2006年に発売を予定していたが、当時は条件がまとまらず、発売中止となっていたものを、このほど条件がまとまり、今回、フジコ・ヘミングの代名詞となっているリストの「ラ・カンパネラ S.141-3」の5つのヴァージョンと合わせて追悼盤として発売。
ピアノのフジコ・ヘミング(1931年―2024年)は、日本人の母とロシア系スェーデン人を父としてベルリンに生まれる。10歳から、父の友人だったロシア生まれドイツ系ピアニストのレオニード・クロイツアー(1884年―1953年)に師事。青山学院高等部在学中、17歳でデビュー・コンサートを果たす。また、東京音楽学校(現・東京芸術大学)在学中には、「NHK毎日コンクール」「文化放送音楽賞」など多数受賞。28歳でドイツへ留学。ベルリン音楽学校を優秀な成績で卒業。その後長年にわたりヨーロッパに在住し、演奏家としてのキャリアを積む。1999年2月11日、フジコのピアニストとしての人生の軌跡を描いたNHKのドキュメント番組「フジコ〜あるピアニストの軌跡〜」が放映され、日本で大反響を巻き起こす。その後、発売されたデビューCD「奇蹟のカンパネラ」は、発売後3ヶ月で30万枚のセールスを記録し、異例の大ヒットとなった。第14回日本ゴールドディスク大賞の「クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤー」他各賞を受賞。その後、1999年10月15日の東京オペラシティコンサートホールでの復活リサイタルを皮切りに、本格的な音楽活動を再開し、国内外で活躍した。2024年4月21日、死去。享年92歳。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年8月22日
チャイコフスキー:歌劇「エフゲニー・オネーギン」 作品24 ポロネーズ①
交響曲 第5番 ホ短調 作品64②
ベートーヴェン:ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス 第1番 ト長調 作品40③
サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ イ短調 作品28④
指揮:ディエゴ・マテウス(①~③)
小澤征爾(④)
ヴァイオリン:アンネ=ゾフィー・ムター(③、④)
管弦楽:サイトウ・キネン・オーケストラ(SKO)
録音:2018年12月、東京、サントリーホール
CD:ユニバーサルミュージック UCCG-41172
このCDは、ドイツ・グラモフォン創立120周年を記念してサントリーホールで行われたガラ・コンサートのライヴ録音。サイトウ・キネン・オーケストラにとって初のサントリーホール公演でもあった。小澤征爾はっ当日最後のサン=サーンス作品を指揮。ムターとサイトウ・キネン・オーケストラも初共演となった記念すべき公演の記録。SKO結成40周年・齋藤秀雄没後50年記念盤。
ヴァイオリンのアンネ=ゾフィ・ムター(1963年生れ)はドイツ、バーデン出身。13歳でカラヤンに招かれ、ベルリン・フィルと共演し、天才少女と言われるきっかけとなる。1977年ダニエル・バレンボイム指揮のイギリス室内管弦楽団と共演して、ザルツブルク音楽祭にデビューした。1980年ズービン・メータ指揮のニューヨーク・フィルと共演して、アメリカ・デビューを飾る。レパートリーは広く、ヴィヴァルディから現代音楽までを扱うが、とりわけ得意は新ウィーン楽派やバルトーク、アンリ・デュティユーなどの近現代の音楽。ヴァイオリンを弾きながらの弾き振りにも精力的な姿勢を見せる。これまでに、グラミー賞を4回受賞。2019年高松宮殿下記念世界文化賞受賞。
指揮の小澤征爾(1935年―2024年)は、満洲国奉天市(中国瀋陽市)に生まれる。齋藤秀雄の指揮教室に入門。桐朋学園短期大学(現在の桐朋学園大学音楽学部)を卒業後、1959年貨物船で単身渡仏。1959年パリ滞在中に第9回「ブザンソン国際指揮者コンクール」第1位となったほか「カラヤン指揮者コンクール」第1位となり、指揮者のヘルベルト・フォン・カラヤンに師事。1960年「クーセヴィツキー賞」を受賞。指揮者のシャルル・ミュンシュ、レナード・バーンスタインに師事。1961年ニューヨーク・フィルハーモニック副指揮者に就任。1970年タングルウッド音楽祭の音楽監督に就任。同年サンフランシスコ交響楽団の音楽監督に就任。1973年にはボストン交響楽団の音楽監督に就任したが、以後30年近くにわたり同楽団の音楽監督を務めた。2002年日本人指揮者として初めて「ウィーン・フィルニューイヤーコンサート」を指揮。同年ウィーン国立歌劇場音楽監督に就任。2008年文化勲章を受章。2010年ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団により、名誉団員の称号を贈呈される。2015年「ケネディ・センター名誉賞」を日本人として初の受賞。2016年ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団により、名誉団員の称号を贈呈される。
指揮のディエゴ・マテウスは、ベネズエラのエル・システマ(ベネズエラで行われている音楽教育プログラムの組織で、1975年に経済学者で音楽家のホセ・アントニオ・アブレウ博士によって設立)出身。クラウディオ・アバドの薫陶を受け、国際的なキャリアを築く。38歳でフェニーチェ劇場首席指揮者、モーツァルト管弦楽団及びメルボルン交響楽団の首席客演指揮者を歴任。日本ではセイジ・オザワ松本フェスティバル、NHK交響楽団等に登場。2018年に開催されたドイツ・グラモフォン120周年記念スペシャル・ガラ・コンサートでは、小澤征爾とともに指揮を務めた。2022年より、小澤征爾音楽塾初となる首席指揮者に就任。ミラノ・スカラ座管弦楽団、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団、ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団などの名門に数多く客演し、ベルリン州立歌劇場、パリ国立歌劇場、トリノ王立歌劇場等にも登場。ベネズエラではシモン・ボリヴァル交響楽団の首席指揮者を務め、エル・システマのさらなる充実にも情熱を注いでいる。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年8月19日

ハイドン:弦楽四重奏曲第31番 ロ短調 Op.33, No.1, Hob.III:37
バルトーク:弦楽四重奏曲第2番 Op.17, Sz.67
弦楽四重奏:クァルテット・インテグラ
三澤響果(ヴァイオリン)
菊野凜太郎(ヴァイオリン)
山本一輝(ヴィオラ)
パク・イェウン(チェロ)
CD:ナミレコード WWCC-8013
名だたる国際コンクール「ミュンヘン」で2位、「バルトーク」で1位の実力。彼らでしか聴けない絶妙なバランスで、曲の核心に迫る。デビューCDに続き、早くも第二弾。
弦楽四重奏団のクァルテット・インテグラは、2015年桐朋学園に在学中のメンバーによりに結成された、メンバーの年齢が全員二十代という若いカルテットである。2021年「バルトーク国際コンクール」弦楽四重奏部門第1位。2022年「ARDミュンヘン国際音楽コンクール」弦楽四重奏部門第2位、併せて、聴衆賞を受賞。第8回「秋吉台音楽コンクール」弦楽四重奏部門第1位、併せて、ベートーヴェン賞、山口県知事賞を受賞。キジアーナ音楽院夏期マスタークラスにて最も優秀な弦楽四重奏団に贈られる「Banca Monte dei Paschi di Siena賞」を受賞。クライブ・グリーンスミス氏、ギュンター・ピヒラー氏の指導を受ける。第41回霧島国際音楽祭に出演し、「堤剛音楽監督賞」及びに「霧島国際音楽祭賞」を受賞。NHK「クラシック倶楽部」、「リサイタル・パッシオ」、「ららら♪クラシック」等に出演。サントリーホール室内楽アカデミー第5,6期フェロー。磯村和英、山崎伸子、原田幸一郎、池田菊衛、花田和加子、堤剛、毛利伯郎、練木繁夫各氏に師事。公益財団法人松尾学術振興財団より助成を受ける。2022年秋よりロサンゼルスのコルバーンスクールにレジデンスアーティストとして在籍。現在、クライブ・グリーンスミス氏、マーティン・ビーヴァー氏に師事。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年8月15日

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調 作品78「雨の歌」
ヴァイオリン・ソナタ第2番イ長調 作品100
ヴァイオリン・ソナタ第3番ニ短調 作品108
パラディス:シチリアーノ
ヴァイオリン:辻 彩奈
ピアノ:阪田知樹
CD:ソニーミュージック SICX-10021
ともに2016年、ふたつの国際コンクール(モントリオール国際コンクール/フランツ・リスト国際コンクール)で第1位を獲得した若きヴィルトゥオーゾ、辻彩奈と阪田知樹。2020年からデュオとして全国各地で公演を行い、表情豊かで鮮度の高いデュオを聴かせてきた。今回、折に触れて取り上げてきたブラームスの3つのヴァイオリンとピアノのためのソナタをセッション・レコーディング。ふたりの公演でアンコールとしてしばしば演奏されたパラディスの「シチリアーノ」も収録。
ヴァイオリンの辻 彩奈は、1997年岐阜県生まれ。3歳よりスズキメソードにてヴァイオリンを始め、10歳時にスズキテンチルドレンに選ばれる。11歳で名古屋フィルハーモニー交響楽団と共演後、多くの国内外のオーケストラと共演。12歳で初リサイタルを行う。2016年「モントリオール国際音楽コンクール」において日本人として初の優勝を飾る。2017年「岐阜県芸術文化奨励」を受賞。2018年第28回「出光音楽賞」受賞。2019年ジョナサン・ノット指揮スイス・ロマンド管弦楽団とジュネーヴおよび日本にてツアーを実施し、その艶やかな音色と表現によって各方面から高い評価を得る。2022年辻 彩奈&阪田知樹デュオ・リサイタルツアーを全国10か所で実施。表情豊かで鮮度の高いデュオを聴かせ、深化著しい二人が触発し合って生み出す音楽は、各方面より称賛を受ける。
ピアノの阪田知樹(1993年生まれ)は、東京藝術大学2年在学中の19歳で、第14回「ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクール」最年少入賞(4~6位)。2012年より、名だたる世界的ピアニストを輩出し続けるイタリア北部の「コモ湖国際ピアノアカデミー」の最年少生徒として認められる。 2014年には、ハノーファー音楽大学に特別首席入学を果たす。「ピティナ・ピアノコンペティション」特級グランプリおよび聴衆賞等5つの特別賞。「クリーヴランド国際ピアノコンクール」にてモーツァルト演奏における特別賞。「キッシンジャー国際ピアノオリンピック」では日本人初となる第1位及び聴衆賞。2016年「フランツ・リスト国際ピアノコンクール」優勝および6つの特別賞受賞。2017年「横浜文化賞文化・芸術奨励賞」受賞。2021年「エリザベート王妃国際音楽コンクール」第4位入賞。2023年第32回「出光音楽賞」受賞。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年8月12日
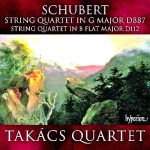
シューベルト:弦楽四重奏曲第15番 ト長調 D887
弦楽四重奏曲第8番 変ロ長調 D112
弦楽四重奏:タカーチ弦楽四重奏団
エドワード・ドゥシンベア(第1ヴァイオリン)
ハルミ・ローズ(第2ヴァイオリン)
リチャード・オニール(ヴィオラ)
アンドラーシュ・フェイェール(チェロ)
CD:Hyperion CDA68423(TMP JCDA-68423)
このCDは、タカーチ弦楽四重奏団の新録音で、若きシューベルトと円熟のシューベルトの弦楽四重奏曲を収録。まだ10代であった若きシューベルトが1814年9月5日から13日までの短い期間に書き上げた弦楽四重奏曲第8番。そしてシューベルトが作った弦楽四重奏曲の最後となった第15番。こちらもわずか11日間で書かれた作品。第15番は、シューベルトの存命中に全曲演奏されることはなかったが、その野心的な作風は彼の室内楽曲を代表するものに値する作品といえる。
タカーチ弦楽四重奏団は、ハンガリー、ブタペストのリスト音楽院教授のアンドラーシュ・ミーハイの門下生であったガボル・タカーチ=ナジら4人の学生によって1975年に結成された。1977年にフランスのエヴィアンで開かれた「国際弦楽四重奏コンクール」で一等賞および批評家賞を受賞したことで一躍を注目を集めた。1978年「ブタペスト国際弦楽四重奏コンクール」優勝、ボルドー音楽祭でゴールド・メダル受賞。その後、アマデウス四重奏団、ハンガリー四重奏団に師事するなど研鑽を積み、世界に知られる弦楽四重奏団に成長を遂げた。現在はアメリカ合衆国のコロラド州ボルダーを拠点としている。2020年、グラミー賞受賞(3度のノミネート)で知られる世界的ヴィオリスト、リチャード・オニールが新たなメンバーとして加わり活動している。
コメント/トラックバック投稿 »