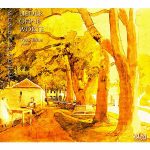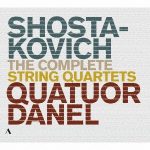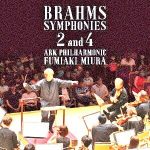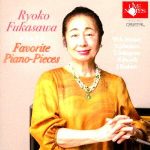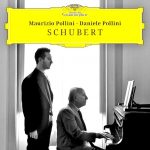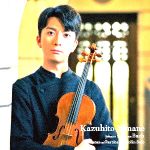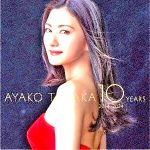2024年10月17日

<CD 1>
ショスタコーヴィチ:交響曲 第4番 ハ短調 作品43
<CD 2>
ショスタコーヴィチ:交響曲 第5番 ニ短調 作品47
交響曲 第6番 ロ短調 作品54
指揮:クラウス・マケラ
管弦楽:オスロ・フィルハーモニー管弦楽団
CD:ユニバーサルミュージック UCCD-45030~31
クラウス・マケラとオスロ・フィルハーモニー管弦楽団との関係が始まった当初から、ショスタコーヴィチの音楽は、彼らのプログラミングの中核をなしており、彼らが交響曲第5番を初めて演奏したのは、マケラが首席指揮者に就任する前の2019年11月であった。
指揮のクラウス・マケラ(1996年生まれ)は、フィンランド出身。シベリウス・アカデミーで指揮とチェロを学ぶ。チェリストとして数々のオーケストラと共演しつつ、10代の頃から指揮者としても頭角を現し、これまでにフィンランド放送響、ヘルシンキ・フィル、ライプツィヒ放送響など、世界の一流オーケストラを指揮し、「数十年に一度の天才指揮者の登場」とも評される大成功を収めている。さらにチェリストとしてフィンランドの主要オーケストラと共演。2020年24歳でオスロ・フィルハーモニー管弦楽団芸術監督・首席指揮者に就任。2021年パリ管弦楽団の音楽監督に就任。また、2027年からロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者に就任する予定。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年10月14日

シューベルト:弦楽四重奏曲第15番ト長調 D887
ウェーベルン:弦楽四重奏のための5つの楽章 Op.5
コジモ・カロヴァーニ:弦楽四重奏曲第10番「In seinem Schatten」
弦楽四重奏:クァルテット・インダコ
エレオノーラ・マツノ(ヴァイオリン)
イダ・ディ・ヴィータ(ヴァイオリン)
ジャミアング・サンティ(ヴィオラ)
コジモ・カロヴァーニ(チェロ)〕
録音:2023年6月17日、クラシカ・ヴィーヴァ・スタジオ(ドルノ、イタリア)
CD:Da Vinci Classics C00871(海外盤/東京エムプラス)
「大阪国際室内楽コンクール&フェスタ」は、「世界7大室内楽コンクール」の1つにも数えられる権威ある音楽コンクールで、コロナ禍による中止を経て6年ぶりに開催された2023年の第1部門(弦楽四重奏)において、見事第1位に輝いたのが、イタリアの実力派弦楽四重奏団「クァルテット・インダコ」。アンサンブル名の「Indaco」は「藍色/インディゴ」を指す言葉。「大阪国際室内楽コンクール&フェスタ」ではイタリアのクァルテットとして初めて優勝し、2つの特別賞(MK記念会賞/ストリング・クァルテット・ビエンナーレ・アムステルダム賞)を受賞した。
弦楽四重奏の「クァルテット・インダコ」は、フィエーゾレ音楽院とハノーファー音楽演劇大学(オリバー・ヴィレの指導のもと、室内楽の修士号を取得)を卒業後、キジアーナ音楽院でギュンター・ピヒラーのマスタークラスを受講。2017年に「スコッティーズ賞」、「プレミオ・パオロ・ボルチアーニコンクール」でファイナリスト選出、「マンハッタン国際コンクール」ゴールドメダル、「大阪国際室内楽コンクール&フェスタ2023」第1位など数々の国際的な賞や奨学金を獲得し、“コンパクトなアンサンブルで、エナメル質と高揚感で満ちている” と表現されている。イタリアの著名な音楽祭や機関に招聘され、ヨーロッパ各地や海外でも定期的に演奏し、今日、同世代のイタリアの弦楽四重奏団の中でも特に注目を集めるアンサンブルであるとみなされている。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年10月10日
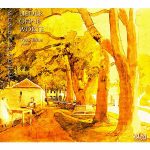
<Disc 1>
第1集 Op. 19
「甘い思い出」ホ長調
「後悔」イ短調
「狩の歌」イ長調
「信頼」イ長調
「眠れぬままに」嬰ヘ短調
「ヴェネツィアの舟歌 第1」ト短調†
第2集 Op. 30
「瞑想」変ホ長調
「安らぎもなく」変ロ短調
「慰め」ホ長調
「道に迷って」ロ短調
「小川」ニ長調
「ヴェネツィアの舟歌 第2」嬰ヘ短調†
第3集 Op. 38
「宵の明星」変ホ長調
「失われた幸福」ハ短調
「詩人の竪琴」ホ長調
「望み」イ長調
「情熱」イ短調
「デュエット」変イ長調†
第4集 Op. 53
「浜辺で」変イ長調
「浮き雲」変ホ長調
「胸さわぎ」ト短調
「悲しい心」ヘ長調
「民謡」イ短調 †
「飛翔」イ長調
<Disc 2>
第5集 Op. 62
「5月のそよ風」ト長調
「門出」変ロ長調
「葬送行進曲」ホ短調
「朝の歌」ト長調
「ヴェネツィアの舟歌 第3」イ短調
「春の歌」イ長調
第6集 Op. 67
「期待」変ホ長調
「失われた幻影」嬰ヘ短調
「巡礼の歌」変ロ長調
「紡ぎ歌」ハ長調
「羊飼いの嘆き」ロ短調
「子守歌」ホ長調
第7集 Op. 85
「夢想」ヘ長調
「別れ」イ短調
「うわごと」変ホ長調
「エレジー」ニ長調
「帰還」イ長調
「旅人の歌」変ロ長調
第8集 Op. 102
「家もなく」ホ短調
「追憶」ニ長調
「タランテラ」ハ長調
「そよ風」ト短調
「子供の小品」イ長調
「信仰」ハ長調
CD:コジマ録音(ALM RECORDS) ALCD-9266~7
ピアノ:徳江陽子
このCDは、ロマン派音楽で花開いた性格的小品の傑作メンデルスゾーン:無言歌集(全48曲)の教則版以外では、日本人初となる全曲録音盤。
ピアノの徳江陽子は、東京都出身。学習院初等科、女子中等科を経て桐朋学園大学付属高校、パリ国立高等音楽院卒業。1964年「学生音楽コンクール」中学生の部で全国優勝。1968年、桐朋学園大学付属高校在学中に、アメリカン・スクール主催青少年コンサートで、秋山和慶氏指揮の東京交響楽団とサン・サーンスのピアノ協奏曲第2番を共演し注目を集める。1973年、パリ国立高等音楽院を卒業後、東京、パリ、ロンドンにてリサイタルを行う。1975年、パリにて「ラヴェル生誕百年祭コンサート」に出演。1977年東京椿山荘学習院常磐会総会にて香淳皇后陛下、高松宮、三笠宮、常陸宮各妃殿下に御前演奏。1979年、イギリス・チェスター市主催音楽コンクールにてピアノ部門最優秀賞を受賞。1998、2000、2002年にはカリフォルニア大学の招聘、2002年には中国藩陽国立音楽院の招聘により、マスタークラスとリサイタルを行う。2005年には40周年記念リサイタルを紀尾井ホールにて行い、好評を博す。その後も、国際交流基金によりエジプト、ブラジルで演奏。南米3大オペラ劇場の一つ、マナウスの「アマゾナス劇場」やサン・パウロのヘブライカクラブの「ルービンシュタイン劇場」で東洋人として、日本人として初リサイタルを行う。2011年より5年計画で、渋谷区共催、司葉子さんを代表として東日本大震災復興支援実行委員会を立ち上げ、チャリティーピアノコンサート(被災している福島県の子供達の為に)を行っている。毎春、光が丘美術館、毎秋、サントリーホールブルーローズでリサイタルを行っている。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年10月07日
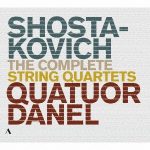
<CD1>
ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲 第1番 ハ長調 Op.49
弦楽四重奏曲 第2番 イ長調 Op.68
弦楽四重奏曲 第3番 ヘ長調 Op.73
<CD2>
ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲 第4番 ニ長調 Op.83
弦楽四重奏曲 第5番 変ロ長調 Op.92
弦楽四重奏曲 第6番 ト長調 Op.101
<CD3>
ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲 第7番 嬰ヘ短調 Op.108
弦楽四重奏曲 第8番 ハ短調 Op.110
弦楽四重奏曲第9番変ホ長調 Op.117
<CD4>
ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲 第10番 変イ長調 Op.118
弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 Op.122
弦楽四重奏曲 第12番 変ニ長調 Op.133
<CD5>
ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲 第13番 変ロ短調 Op.138
弦楽四重奏曲 第14番 嬰ヘ長調 Op.142
<CD6>
ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲 第15番 変ホ短調 Op.144
エレジー(アダージョ)弦楽四重奏のための
(歌劇《ムツェンスク郡のマクベス夫人》Op.29
第1幕第3場のカテリーナのアリア)
ポルカ(アレグレット)弦楽四重奏のための(バレエ《黄金時代》からのポルカ)
未完成の弦楽四重奏曲
録音:メンデルスゾーンザール、ゲヴァントハウス小ホール、ライプツィヒ、2022年2月6~10日、5月1~5日(ライヴ録音)
弦楽四重奏:ダネル弦楽四重奏団
マルク・ダネル(第1ヴァイオリン)
ジル・ミレ(第2ヴァイオリン)
ヴラッド・ボグダナス(ヴィオラ)
ヨヴァン・マルコヴィッチ(チェロ)
CD:キングインターナショナル KKC‐6861~6(6枚組)
このCDアルバムは、全曲演奏回数34回のダネル四重奏団による二度目の「ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲全集」録音(2022年にライプツィヒのメンデルスゾーン・ザールでライヴ録音)。
ダネル弦楽四重奏団は、1991年ベルギーのブリュッセルで結成された。アマデウス弦楽四重奏団、ボロディン弦楽四重奏団、ベートーヴェン弦楽四重奏団等のもとで学び、結成後数年で国際的に活躍の幅を広げる。1993年サンクトペテルブルクの「ショスタコーヴィチ国際弦楽四重奏コンクール」第1位、1994年「ロンドン国際弦楽四重奏コンクール」第3位、1995年「エヴィアン国際弦楽四重奏コンクール」第2位及び国際プレスの審査員特別賞を受賞。世界各地の主要なコンサートでの演奏、一連の画期的なCD録音などにより、常に世界の音楽シーンを先導する。伝統的な弦楽四重奏曲に新たな視点から生気を吹き込む演奏は各方面から称賛されている。また、リーム、ラッヘンマン、グバイドゥーリナ、デュサパン、ヴィットマン、マントヴァーニといった主要な現代作曲家とのコラボレーションも彼らの強みとなっている。レパートリーは幅広く、これまでにハイドン、ベートーヴェン、シューベルト、ショスタコーヴィチ、ヴァインベルクの弦楽四重奏曲のツィクルスに取り組んだ。2005年にリリースしたショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲全曲録音は画期的な解釈のひとつとして今なお評価されている。2023年からロンドンのウィグモア・ホールのレジデンス・カルテットとして活動。日本には、2005年の初来日以降度々来日し、好評を得ている。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年10月03日
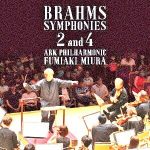
<DISC 1>
ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73
<DISC 2>
ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98
CD:エイベックス AVCL-84160~61
指揮:三浦文彰
管弦楽:ARK PHILHARMONIC(ARKフィル)
その高い音楽性から、ヴァイオリン、指揮ともに欧米でも高い評価を受ける三浦文彰が、トッププレイヤーが集結したドリームオーケストラARK PHILHARMONIC(ARKフィル)と共に問う、CDアルバム。
ヴァイオリン・指揮の三浦文彰(1993年生まれ)は、東京都出身。6歳から徳永二男氏に師事。その後、ウィーン私立音楽大学で学ぶ。2006年「ユーディ・メニューイン国際ヴァイオリンコンクール」第2位。そして2009年、世界最難関とも言われる「ハノーファー国際コンクール」において、史上最年少の16歳で優勝。その後、モスクワ、ドイツ、スイスなどで開催される音楽祭に数多く出場。さらに北ドイツ放送交響楽団やウィーン室内管弦楽団などのオーケストラと共演するなど、国際的な活動を展開する。2018年からスタートした「サントリーホールARKクラシックス」ではアーティスティック・リーダーに就任。ロンドンの名門ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団のアーティスト・イン・レジデンスも務める。2009年度第20回「出光音楽賞」受賞。2022年に雑誌「Forbes」(アジア版)において「30 under 30(世界を変える30歳未満の30人)」に選出された。
ARK PHILHARMONIC(略称:ARKフィル)は、毎年10月にサントリーホールを舞台に繰り広げられる都市型の音楽祭「サントリーホール ARK クラシックス」のレジデント・オーケストラとして2019年に「ARKシンフォニエッタ」の名称で発足。「サントリーホールARKクラシックス」のアーティスティック・リーダーを務める辻井伸行と三浦文彰の呼びかけにより、ソリストとしても活躍するフルートの高木綾子やチェロの遠藤真理、コンサートマスターや首席奏者として日本のオーケストラ界を牽引する三浦章宏、高橋和貴、松浦奈々、会田莉凡、鈴木康浩などが中心的な役割を担い、国内外のコンクールで優勝を飾った期待の若手奏者らが伸びやかに演奏を繰り広げ、日本最高峰のオーケストラのひとつと賞賛される。編成の拡大に伴い2024年より名称を「ARKフィルハーモニック 」(略称:ARKフィル)に変更し、アーティスティック・ディレクターに三浦文彰が、レジデンス・ピアニストに辻井伸行が就任。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年9月30日

<Disc 1>
シューベルト:4つの即興曲作品142、D935 第1番ヘ短調
4つの即興曲作品142、D935 第2番変イ長調
4つの即興曲作品142、D935 第3番変ロ長調
4つの即興曲作品142、D935 第4番ヘ短調
<Disc 2>
シューベルト:ピアノ・ソナタ第19番ハ短調D958
宗教的歌曲 S562 第1曲 連祷
12のリート S558 第7曲 春の想い
ロンド イ長調D951
ピアノ:小林愛実
反田恭平
録音:2024年5月20日~23日、ベルリン、テルデックス・スタジオ
CD:ワーナーミュージック WPCS-13868~9
小林愛実、人生の大きな節目を超えて到達した至高の境地、初のシューベルト録音。3年ぶり。結婚、出産からの休養期間を経て待望の最新録音、初のシューベルト作品。アルバム。ソナタ第19番は小林自身がシューベルト作品として初めて手がけた縁の楽曲。夫妻共演による初の公式録音曲(ロンド イ長調)も収録。輸入盤には収録されない小品2曲(リスト編曲の「春の想い」「連祷」)も完全収録(日本盤のみの収録)。
ピアノの小林愛実(1995年生まれ)は、山口県宇部市出身。 2005年「全日本学生音楽コンクール」小学生部門で全国優勝。2009年「アジア太平洋国際ショパンピアノコンクール(韓国)」でJr部門優勝。2011年「ショパン国際コンクールin Asia」コンチェルトで金賞を受賞。第5回「福田靖子賞」受賞。2009年サントリーホールにおいてメジャー・デビュー記念コンサートを開催したが、同ホールソロとしては、日本人最年少記録および女性ピアニスト最年少記録。2011年桐朋女子高等学校音楽科に入学。2013年米国カーティス音楽院に留学。海外では、アメリカ、フランス、ポーランド、ブラジル等で演奏。2011年カーネギー・ホールにおいて、小澤征爾が芸術監督を務めた”日本フェスティヴァル”においてソロ・リサイタルを行う。2012年「ジーナ・バッカウアー国際ピアノコンクール」のヤングアーティスト部門で第3位入賞。2015年第17回「ショパン国際ピアノコンクール」ファイナリスト。2021年第18回「ショパン国際ピアノコンクール」第4位入賞。2022年第31回「出光音楽賞」受賞。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年9月26日
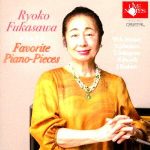
モーツァルト:ピアノ・ソナタ ハ長調K.330
シューベルト:楽興の時D780 作品94
助川敏弥:夜の詩(うた)(2002)
夢逢い(2006)
Prelude 春(2010)
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲 BB68
ブラームス:幻想曲 作品116 より
第2番 イ短調 間奏曲
第5番 ホ短調 間奏曲
第6番 ホ長調 間奏曲
第7番 ニ短調 奇想曲
ピアノ:深沢亮子
CD:ナミ・レコード WWCC-8015
このCDは、日本ピアノ界のレジェンド、深沢亮子が収録した最新盤。「現在の彼女が到達した至高の境地を象徴する非凡な名演」(柴田龍一)。
ピアノの深澤亮子は、千葉県東金市出身。第22回「日本音楽コンクール」第1位。17才でウィーン国立音楽大学に留学。1959年同校を首席で卒業。1961年「ジュネーブ国際音楽コンクール」で1位なしの 2位入賞。1992年国際交流基金より音楽文化使節として派遣され、ルーマニア、チェコ、スロバキア、ブルガリアで演奏旅行。1995年千葉県より文化功労者として顕彰。2005年東金市政特別功労者、英国ケンブリッジ国際伝記センター(IBC)により 「最も優秀な100人の音楽家」の1人に選ばれる。現在、日本音楽舞踊会議代表理事。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年9月23日
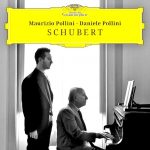
シューベルト:ピアノ・ソナタ 第18番 ト長調 作品78 D894(マウリツィオ・ポリーニ)
楽興の時 D. 780(ダニエレ・ポリーニ)
幻想曲 ヘ短調 D 940(マウリツィオ・ポリーニとダニエレ・ポリーニの連弾)
ピアノ:マウリツィオ・ポリーニ
ダニエレ・ポリーニ
録音:2022年6月、ミュンヘン、ヘラクレスザール
CD:ユニバーサル ミュージック UCCG-45108
2024年3月に急逝したイタリアの偉大なピアニスト、マウリツィオ・ポリーニ。2022年6月、ポリーニが生前最後に録音したこのCDは、息子でピアニストのダニエレとの共演作。2人が一緒に連弾曲を演奏するのはこのCDが初めて。収録曲には、2人が愛するシューベルトのピアノ作品を取り上げている。ポリーニの演奏による“幻想ソナタ”の愛称で知られる「ソナタ第18番」、ダニエレによる「楽興の時」、そして2人の連弾による「幻想曲 ヘ短調」でアルバムが締めくくられる。
マウリツィオ・ポリーニ(1942年―2024年)は、イタリア、ミラノ出身。1957年15歳で「ジュネーブ国際コンクール」第2位。1960年18歳で第6回「ショパン国際ピアノコンクール」審査員全員一致で優勝し、一躍国際的な名声を勝ち取る。その後10年近く、表だった演奏活動から遠ざかる。1968年に演奏活動に復帰。現役では最も高い評価を受けているピアニストの一人であった。演奏の正確さから「精密機械」とも称された。 2014年に完成したポリーニによるベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集は、全集の完成までに39年を要した。そして近年、新たなベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集の再録音に取り組んでいた。1974年に初来日して以降、たびたび日本も訪れていた。2010年「高松宮殿下記念世界文化賞(音楽部門)」受賞。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年9月19日
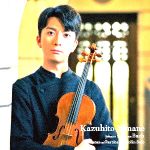
<CD1>
J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト短調 BWV1001
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第1番 ロ短調 BWV1002
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ短調 BWV1003
<CD2>
J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番 二短調 BWV1004
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番 ハ長調 BWV1005
無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番 ホ長調 BWV1006
ヴァイオリン:山根一仁
CD:キングレコード KICC-1621~2(2枚組)
このCDは、中学三年生在学中、国内最高峰の日本音楽コンクール (2010年)で第一位を獲得し、各賞を総なめにして以来、業界が最も注目していたヴァイオリニスト、山根一仁が、満を持して発売するデビューCD。
ヴァイオリンの山根一仁(1995年生まれ)は、札幌出身。2014年桐朋女子高等学校音楽科(共学)首席卒業。同大学ソリスト・ディプロマ・コースを経て、2015年よりドイツ国立ミュンヘン音楽演劇大学に留学。第79回「日本音楽コンクール」第1位および岩谷賞(聴衆賞)など5つの副賞受賞。第60回「横浜文化賞文化・芸術奨励賞」最年少受賞。2012年「Foundation for Youth賞」(岩谷時子音楽文化振興財団)受賞。2015年「青山音楽賞」新人賞、2015年第26回「出光音楽賞」受賞。2017年第19回「ホテルオークラ音楽賞」受賞。
コメント/トラックバック投稿 »
2024年9月16日
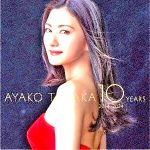
ロジャース(日本語版):エーデルワイス
ヨハン・シュトラウス2世:美しく青きドナウ
モーツァルト:夜の女王のアリア
私の感謝をお受けください、慈悲の人よ
アヴェ・ヴェルム・コルプス
バッハ:ああ、なんて美味しいの、コーヒーは!
シューベルト:アヴェ・マリア
ヘンデル:私を泣かせてください
パガニーニ/クライスラー:ラ・カンパネラ
ラフマニノフ:ヴォカリーズ
ドビュッシー:月の光
プライズマン:アヴェ・マリア
チック・コリア:ホワット・ゲーム・シャル・ウィ・プレイ・トゥデイ
ロジャース:サウンド・オブ・ミュージック
ヨハン・シュトラウス2世:春の声
ソプラノ:田中彩子
ピアノ:加藤昌則、佐藤卓史、山中惇史
チェロ:植木昭雄、西山健一
ヴァイオリン:杉田せつ子、俣野賢仁
ヴィオラ:柳原有弥
ペーター・イレイニ指揮ブダペスト・アート交響楽団
CD:avex-CLASSICS AVCL-84166
このCDは、ウィーンを拠点に活躍を繰り広げるハイコロラトゥーラの田中彩子が、鮮烈なデビューを飾ったアルバム「華麗なるコロラトゥーラ」発売から10周年を記念して、これまでに発表した4枚のアルバムからセレクションしたベスト盤。
ソプラノの田中彩子(1984年生まれ)は、京都府舞鶴市出身。18歳で単身ウィーンに留学。22歳のときスイス・ベルン州立歌劇場にて同劇場最年少でソリスト・デビューを飾り、6ヶ月というロングラン公演を代役なしでやり遂げる。翌年、「国際ベルヴェデーレオペラ・オペレッタコンクール」ではオーストリア代表として本選出場を果たす。ウィーン・フォルクスオーパーとオッフェンバック「ホフマン物語」のオランピア役のカバーを務めたことを皮切りに、オーストリア政府公認スポンサーの「魔笛」公演では、夜の女王役として2012年から3年に渡って出演。その後、コンサート・ソリストとしてヨーロッパ、南米各地のオーケストラ公演に出演など、世界で活躍。日本でもコンサートのみならずメディア出演も多い。2018年「アルゼンチン最優秀初演賞」受賞。 2019年 「Newsweek日本版」の「世界が尊敬する日本人100人」に選出。2020年発売CD「Esteban Benzecry」は、イギリスBBCクラシック専門音楽誌にて5つ星に評された。音楽や芸術を通じた教育・国際交流活動を行う「Japan Association for Music Education Program」を設立し代表理事を務める。舞鶴市文化親善大使、京丹後市文化国際交流アドバイザー、宮津市文化芸術ブランドアンバサダーにも就任。ウィーン在住。
コメント/トラックバック投稿 »