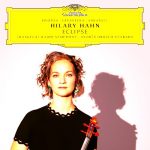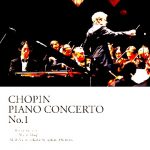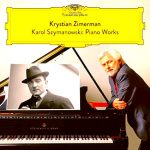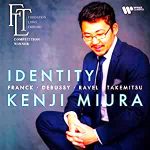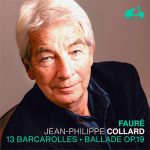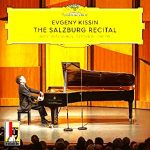2022年11月24日
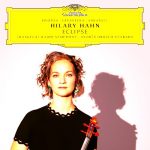
ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲 イ短調 作品53
ヒナステラ:ヴァイオリン協奏曲 作品30
サラサーテ:カルメン幻想曲 作品25
ヴァイオリン:ヒラリー・ハーン
指揮:アンドレス・オロスコ=エストラーダ
管弦楽:フランクフルト放送交響楽団
CD:ユニバーサル ミュージック UCCG-45062
ヴァイオリンのヒラリー・ハーン(1979年生れ)は、アメリカ、バージニア州レキシントン出身。1991年11歳の時に初リサイタル。その後、クリーヴランド管弦楽団、ピッツバーグ交響楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ニューヨーク・フィルハーモニックなどと協演。1997年デビューアルバムである「バッハ:無伴奏ソナタ・パルティータ集」が「ディアパゾン・ドール賞」を受賞。1999年カーティス音楽学校を卒業。2003年ネヴィル・マリナー指揮のアカデミー室内管弦楽団とのブラームスとストラヴィンスキーのヴァイオリン協奏曲の録音により「グラミー賞」受賞。現在、世界中で演奏活動を続ける世界を代表するヴァイオリニストの一人。
指揮のアンドレス・オロスコ=エストラーダ(1977年生れ)はコロンビア出身。ウィーン国立音楽大学で学ぶ。いくつかの歌劇場の指揮者、ウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団の首席指揮者を経て、2014年から、Hr交響楽団の首席指揮者、ヒューストン交響楽団の音楽監督を務める。さらに、2015年からはロンドン・フィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者も務めている。
コメント/トラックバック投稿 »
2022年11月21日
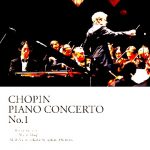
ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11
ピアノ:角野隼斗
指揮:マリン・オルソップ
管弦楽:ポーランド国立放送交響楽団
CD:イープラス EM-25(タワーレコード)
発売:2022年12月21日
このCDは、2022年9月のマリン・オルソップ指揮ポーランド国立放送交響楽団の来日ツアーに、角野がソリストとして参加し演奏されたショパン: ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 作品11」をザ・シンフォニーホールにおいてライヴ録音。今回の来日ツアーは23年ぶり。指揮のマリン・オルソップは、バーンスタインの愛弟子で、名だたる楽団の音楽監督を歴任している巨匠。ショパンコンクールで一躍脚光を浴びた新世代のピアニスト角野隼斗が、ショパンの故郷であるポーランドの名門オーケストラ、一流の指揮者と共演した記念碑的ライヴ録音。
初回盤にはボーナス・トラックとして角野がショパンからインスパイアを受けて作曲したオリジナル楽曲「胎動」「追憶」を特別収録(初CD化)。
ピアノの角野隼斗(1995年生まれ)は、千葉県八千代市出身。2014年に開成高校から東京大学理科一類に進学。東京大学大学院進学後は情報理工学系研究科創造情報学専攻にて機械学習を用いた自動採譜と自動編曲について研究。2018年ピティナ・ピアノコンペティション(PTNA/ピティナ)特級にグランプリを受賞。これにより音響工学研究者に加え音楽家になる決意を固め、プロピアニストとして活動を始める。2018年フランス音響音楽研究所 (IRCAM) に留学し、音楽情報処理の研究に従事。2019年に東大POMPの先輩らと男女混成6人のシティソウルバンド「Penthouse」を結成し、Cateen名義でPf.(ピアノ/キーボード)を担当。同年「リヨン国際ピアノコンクール」第3位。2020年東京大学総長大賞を受賞し、大学院(修士課程)を修了。2021年第18回「ショパン国際ピアノコンクール」三次予選進出(セミファイナリスト)。自身のYouTubeチャンネルでは「Cateen かてぃん」名義で活動し、チャンネル登録者数は100万人、総再生回数は1億1600万回を超えている。
指揮のマリン・オールソップ(1956年生まれ)は、アメリカ、ニューヨーク、マンハッタン出身の女性指揮者。イェール大学に進学した後、ジュリアード音楽院で修士・博士号(ヴァイオリン科)を取得。1989年、タングルウッド音楽祭「クーセヴィツキー賞」を受賞し、レナード・バーンスタイン、小澤征爾らに教えを受けた。1980年代にはジャズとクラシック音楽の融合を目指した活動に力を入れており、1981年にビッグバンド室内アンサンブル「ストリング・フィーヴァー」を立ち上げる。1984年に組織したコンコーディア管弦楽団は、ジャズとのクロスオーヴァーを主体としている。コロラド交響楽団音楽監督(1993年―2005年)、ボーンマス交響楽団首席指揮者(2002年~2008年)を歴任。2007年ボルティモア交響楽団音楽監督に就任。これによりオールソップは、アメリカで初めてメジャー・オーケストラの音楽監督を務める女性指揮者となった。
ポーランド国立放送交響楽団は、ポーランド南部の都市カトヴィツェを本拠地とするオーケストラ。1935年、ワルシャワで設立された。結成を主導した指揮者・作曲家のグジェゴシュ・フィテルベルクが初代の首席指揮者。第二次世界大戦の勃発と共に一時活動停止を余儀なくされるが、1945年3月、ポーランドの指揮者ヴィトルド・ロヴィツキによりカトヴィツェで再結成され、その後再びフィテルベルクが芸術監督に就任。以降はヤン・クレンツ、ボフダン・ヴォディチコが後を継ぎ、タデウシュ・ストルガーラ、イェジー・マクシミウク、スタニスワフ・ヴィスウォツキ、ヤツェク・カスプシク等が音楽監督を務めた後、1983年からはアントニ・ヴィトが17年間にわたって芸術監督を務めた。ヴィトの後任はガブリエル・フムラ(2001年~2007年、音楽監督)で、2009年よりヤツェク・カスプシクが音楽監督に再度就任し、2012年からはアレクサンダー・リープライヒが芸術監督兼首席指揮者を務めている。
コメント/トラックバック投稿 »
2022年11月17日

<Disc1>
リスト:愛の夢 第3番
ヘンツェ:トリスタン-ピアノ、テープと管弦楽のための前奏曲
<Disc2>
ワーグナー(Z. コチシュ編):楽劇「トリスタンとイゾルデ」-第1幕への前奏曲
マーラー(R. スティーヴンソン編):交響曲第10番 嬰ヘ長調より アダージョ
リスト:超絶技巧練習曲より 第11曲 変ニ長調「夕べの調べ」
ピアノ:イゴール・レヴィット
指揮:フランツ・ウェルザー=メスト
管弦楽:ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
CD:ソニーミュージック SICC-30609~10(2枚組)
人生と存在に関する偉大な問いを探求し、有名なレパートリーから非常に珍しいレパートリーまでを網羅してきたイゴール・レヴィット。今回の新作CDのテーマは「トリスタン」。
イゴール・レヴィット(1987年生まれ)は、ソビエト連邦、ニジニ・ノヴゴロド出身。1995年、8歳の時、22万人以上いるユダヤ人難民の一員として人道的な理由で入国を認められ、家族とドイツのハノーファーに移住する。2000年ハノーファー音楽大学に入学。2004年「マリア・カラス国際グランプリ」第2位。2004年第9回「浜松国際ピアノアカデミー」優勝。2005年第11回「ルービンシュタイン国際ピアノコンクール」第2位。2009年ハノーファー音楽大学ピアノ科を修了。2010年ハノーファー音楽大学史上最高得点でディプロマを取得。2019年ハノーファー音楽大学のピアノ教授に就任。2022年 「ハイデルベルクの春」音楽祭の芸術監督に任命される。
コメント/トラックバック投稿 »
2022年11月14日

R.シュトラウス: アルプス交響曲 作品 64
指揮:小泉和裕
管弦楽:名古屋フィルハーモニー交響楽団
録音:2022年4月15~16日、愛知県芸術劇場コンサートホール(ライヴ録音)
小泉和裕は、音楽監督就任後、名古屋フィルとのコンビで幾多の名演奏を世に送り出してきた。この500回記念定期演奏会で選ばれたのはR.シュトラウス: アルプス交響曲。
指揮の小泉和裕は、1949年京都市生まれ。東京芸術大学大学で山田一雄に師事。第3回「カラヤン国際指揮者コンクール」第1位。その後ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮してベルリン・デビューを飾り、ベルリン・フィルの定期演奏会にも出演。また、米国でシカゴ交響楽団の定期演奏会に出演。2008年から日本センチュリー交響楽団音楽監督、2013年から九州交響楽団音楽監督・首席指揮者、2016年から名古屋フィルハーモニー交響楽団音楽監督を務めている。2014年から東京都交響楽団の終身名誉指揮者。
コメント/トラックバック投稿 »
2022年11月10日
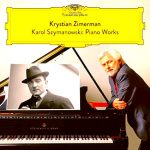
シマノフスキ:9つの前奏曲 作品1 から 第1番、第2番、第7番、第8番
仮面劇 作品34 第1曲:シェヘラザード、第2曲:道化師タントリス、
第3曲:ドン・ファンのセレナーデ
20のマズルカ 作品50 から 第13番、第14番、第15番
ポーランド民謡の主題による変奏曲 作品10、主題、第1変奏~第10変奏
ピアノ:クリスチャン・ツィメルマン
CD:ユニバーサルミュージック UCCG45059
2021年の”ベートーヴェン・プロジェクト”に続き、ツィメルマンが自身の故郷ポーランドのルーツに戻り、2022年生誕140周年を迎えるカロル・シマノフスキのピアノ曲を演奏。ツィメルマンが28年をかけて研究を重ね、録音に挑んだ新作。コペンハーゲンのティヴォリ・コンサートホールとツィメルマンの友人である豊田泰久氏が設計を手掛けた広島県福山市のふくやま芸術文化ホールにて録音された。
ピアノのクリスチャン・ツィメルマン(1956年生れ)は、ポーランド出身。1973年「ベートーヴェン国際音楽コンクール」優勝。1975年第9回「ショパン国際ピアノコンクール」に史上最年少の18歳で優勝。1999年には、ショパン没後150年を記念して、ポーランド人の若手音楽家をオーディションで集めた「ポーランド祝祭管弦楽団」を設立した。2005年、フランスのレジオン・ドヌール勲章(シュバリエ章)を受章。
コメント/トラックバック投稿 »
2022年11月07日
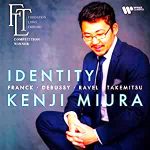
フランク(ハロルド・バウアー編):前奏曲、フーガと変奏曲 ロ短調 Op.18
武満徹:ピアノのためのロマンス
雨の樹素描II(オリヴィエ・メシアンの追憶に)
ラヴェル:水の戯れ
高雅で感傷的なワルツ M.61
ドビュッシー:6つの古代のエピグラフ
喜びの島
<ボーナス・トラック>
ゴダール:マズルカ第2番 変ロ長調 Op.54
ピアノ:三浦謙司
CD:ワーナーミュージック・ジャパン 9029.615458
ピアノの三浦謙司(1993年生まれ)は、兵庫県神戸市出身。現在ドイツ在住。4歳から自主的にピアノを開始し、13歳で奨学金を獲得して単独渡英、ロンドンのパーセル・スクールに入学。2011年にロンドンの王立音楽アカデミー、ベルリン芸術大学及びアメリカのカーティス音楽院に合格。最終的にベルリン芸術大学に入学。2012年の夏、ベルリン芸術大学を中退し、一時的に音楽の世界から離れる。2014年ハンス・アイスラー音楽大学ベルリンに入学する。そして2019年「ロン・ティボー・クレスパン国際コンクール」で優勝し、同時に3つの特別賞を受賞した。これまで、第4回「マンハッタン国際音楽コンクール」金賞、第1回 「Shigeru Kawai 国際ピアノコンクール」優勝、2017年「スタインウェイコンクールベルリン」優勝、第9回「浜松国際ピアノコンクール」奨励賞およびAAF賞などを受賞。
コメント/トラックバック投稿 »
2022年11月03日
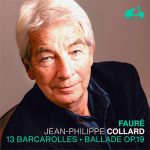
ピアノ:ジャン=フィリップ・コラール
CD:キングインターナショナル LDV-91
フォーレ:13の舟歌
第1番 イ短調 作品26
第2番 ト長調 作品41
第3番 変ト長調 作品42
第4番 変イ長調 作品44
第5番 嬰ヘ短調 作品66
第6番 変ホ長調 作品70
第7番 ニ短調 作品90
第8番 変ニ長調 作品96
第9番 イ短調 作品101
第10番 イ短調 作品104/2
第11番 ト短調 作品105
第12番 変ホ長調 作品106bis
第13番 ハ長調 作品116
バラード 嬰へ長調 作品19
ピアノ:ジャン=フィリップ・コラール
ジャン=フィリップ・コラール(1948年生まれ)は、フランス、シャンパーヌ地方のマルイユ・スィル・アイ出身。パリ音楽院にてピエール・サンカンに師事。1969年「ロン=ティボー国際コンクール」5位入賞。1970年第2回「国際シフラ・コンクール」優勝。フォーレ、ドビュッシー、ラヴェルといった近代フランス音楽のピアノ曲の専門家として知られるほか、ラフマニノフの卓越した解釈によっても知られている。ソリストとして世界各地で演奏旅行を続けているほか、各国の数々の名オーケストラとも共演を重ねている。また室内楽の演奏にも卓越した演奏と繊細鋭敏な感覚を発揮して評価が高い。2003年「レジオン・ドヌール騎士章」受勲。
コメント/トラックバック投稿 »
2022年10月31日

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 Op.98
バッハ:管弦楽組曲第2番 ロ短調 BWV1067
指揮:カール・シューリヒト
管弦楽:スイス・ロマンド管弦楽団
録音:1952年5月3日、1955年8月4日(スイス・ロマンド放送によるモノラル録音)
CD:キングインターナショナル Altus ALT520
指揮のカール・シューリヒト(1880年―1967年)は、ドイツ出身の20世紀で最も重要な指揮者の一人。1923年から1944年までヴィースバーデンの音楽総監督を務め、マーラーの作品の解釈で国際的な名声を得た。また、ライプツィヒ交響楽団(現:MDR交響楽団)首席指揮者(1931-1933)、ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者(1944)、ベルリン・フィルハーモニー合唱団芸術監督(1933-1934)を務めた。第二次世界大戦の終戦前にドイツを離れ、スイスに移住。以後、コンセルトヘボウ管弦楽団、スイス・ロマンド管弦楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団などの客演指揮者として活躍。特にウィーン・フィルハーモニー管弦楽団とは親密な関係を築き、1960年にはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の名誉指揮者に任命された。ザルツブルク音楽祭にも何度か出演し、海外ツアーでも国際的な成功を収めた。
コメント/トラックバック投稿 »
2022年10月27日
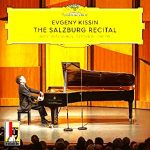
<CD 1>
ベルク:ピアノ・ソナタ 作品1
フレンニコフ:ピアノのための3つの小品 作品5から 第3曲:舞曲
ピアノのための5つの小品 作品2
ガーシュウィン:3つの前奏曲
<CD 2>
ショパン:夜想曲 作品62 第1番 ロ長調(第17番)
即興曲 第1番 変イ長調 作品29
即興曲 第2番 嬰ヘ長調 作品36
即興曲 第3番 変ト長調 作品51
スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20
ポロネーズ 変イ長調 作品53 《英雄》
(アンコール)
メンデルスゾーン:無言歌集 作品38 第6曲 変イ長調 《デュエット》
キーシン:4つのピアノ小品 作品1 第2曲:ドデカフォニック・タンゴ
ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31
ドビュッシー:ベルガマスク組曲 第3曲:月の光
ピアノ:エフゲニー・キーシン
CD:ユニバーサルミュージック UCCG-45055~6
このCDは、2021年7月に98歳で逝去したキーシン唯一の師、アンナ・カントールに捧げた「ザルツブルク音楽祭」祝祭大劇場でのライヴ録音盤。
ピアノのエフゲニー・キーシン(1971年生れ)は、ロシア、モスクワ出身。11歳で初リサイタルを開くなど、幼い頃から神童ぶりを発揮。12歳の時、ドミトリー・キタエンコの指揮するモスクワ・フィルハーモニー管弦楽団で弾いたショパンのピアノ協奏曲が発売され、世界の注目を浴びる。コンクール入賞歴こそほとんどないが、現在、国際的ピアニストとして世界各地で演奏。1986年初来日以降、しばしば日本を訪れている。
コメント/トラックバック投稿 »
2022年10月24日

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
ピアノ:辻井伸行
指揮:ウラディーミル・アシュケナージ
管弦楽:シドニー交響楽団
録音:2016年10月20日-22日、シドニー・オペラハウス コンサートホール(ライヴ録音)
CD:エイベックス・クラシックス AVCL-84139
このCDは、辻井伸行のCDデビュー10周年記念のボックスからの分売で、辻井が敬愛する巨匠アシュケナージとシドニーのオペラハウスで共演したコンサートのライヴ・レコーディング。ピアニストとしても指揮者としても完全にこの曲を手中に収めているアシュケナージによる万全のサポートの下、辻井の演奏がシドニー・オペラハウスを包み込む。シドニーの聴衆の心を打った演奏を余すところなく収めた録音。
コメント/トラックバック投稿 »